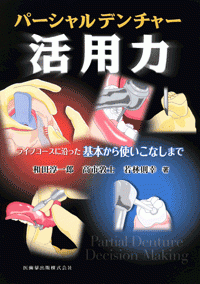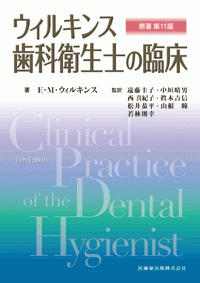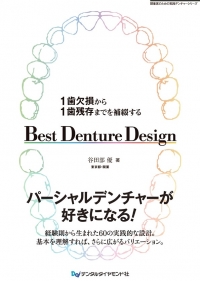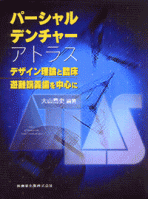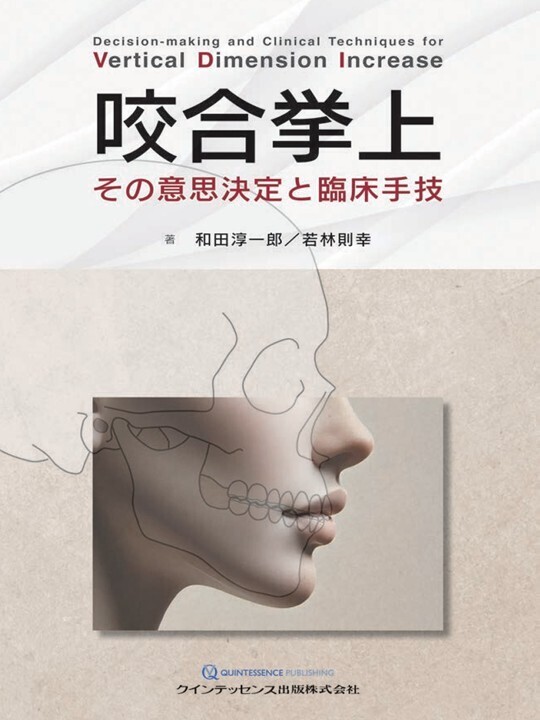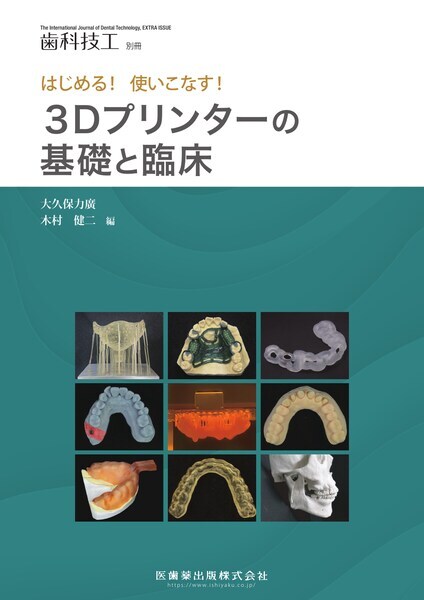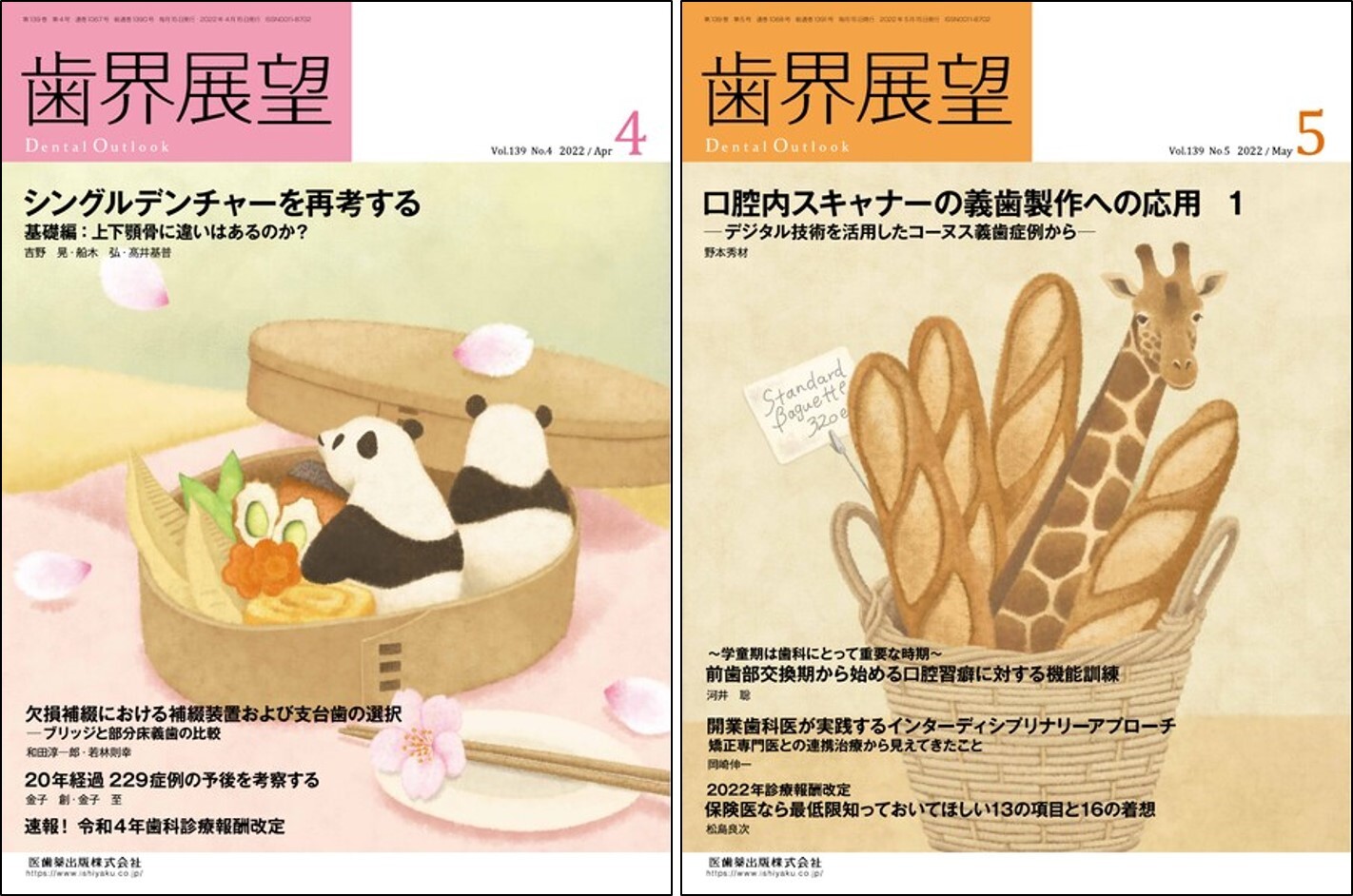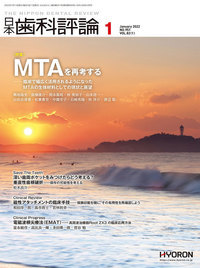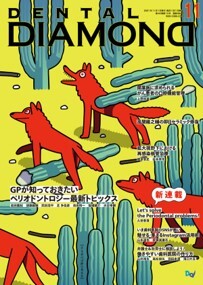関連図書
主な教育向け図書
当分野医局員が執筆した教科書が発売されました.
様々な症例におけるパーシャルデンチャーの有効な活用法,パーシャルデンチャーの臨床の基本から応用まで幅広い情報を,オールカラーで分かり易く説明しています.
本分野が監訳に参加した教科書が発刊されました.
歯科衛生士が習得すべき臨床のすべてを体系的にまとめた,「歯科衛生士のバイブル」と言える一冊です.
個人で持つことはもちろん,診療所,病院,教育施設に常備すべき本として,推薦いたします.
経験則から生まれた60の実践的な設計.
基本を理解すれば,さらに広がるバリエーション.

商業誌等での特集
咬合挙上 その意思決定と臨床手技(2025年3月)
当分野の和田講師,若林教授が執筆した「咬合挙上 その意思決定と臨床手技」がクインテッセンス出版より出版されました(2025年3月11日).
補綴治療時に咬合高径の増大,すなわち咬合挙上の必要性に迫られることがありますが,咬合挙上の諸事項についてはさまざまな考え方があり、ときに悩ましい問題になります.本書は,月刊誌「ザ・クインテッセンス」2021年3~6月に4回にわたり掲載された連載「咬合挙上の今あるエビデンスと臨床手技教えます」の内容を大幅に改編したものです.国内外の文献をあらためて渉猟し,咬合学の基本的事項をふまえつつ学問的に,かつ臨床的にまとめた1冊です.
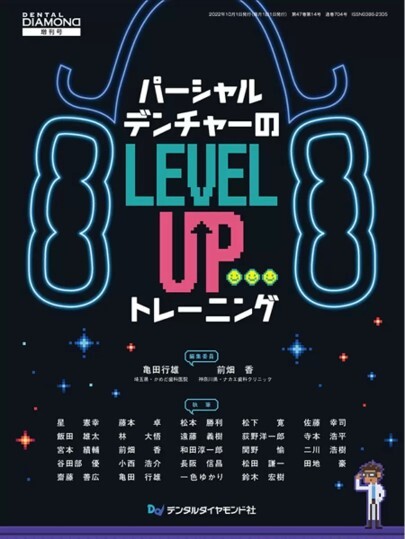
パーシャルデンチャーの"LEVEL UP"トレーニング
当分野の和田助教,谷田部臨床教授の上梓した記事が掲載された書籍が刊行されました.
第1章 診査・診断
Lv.3 難症例を見極めるポイント(谷田部優)
第4章 印象・咬合採得
Lv.1 印象と咬合採得(和田淳一郎)

ザ・クインテッセンス 2023年3月号
当分野の和田助教の上梓した記事が,ザ・クインテッセンス2023年3月号に掲載されました.
時代をつかむトピックス
海外便りトゥルク発 フィンランドで感じた日本との意外な共通点
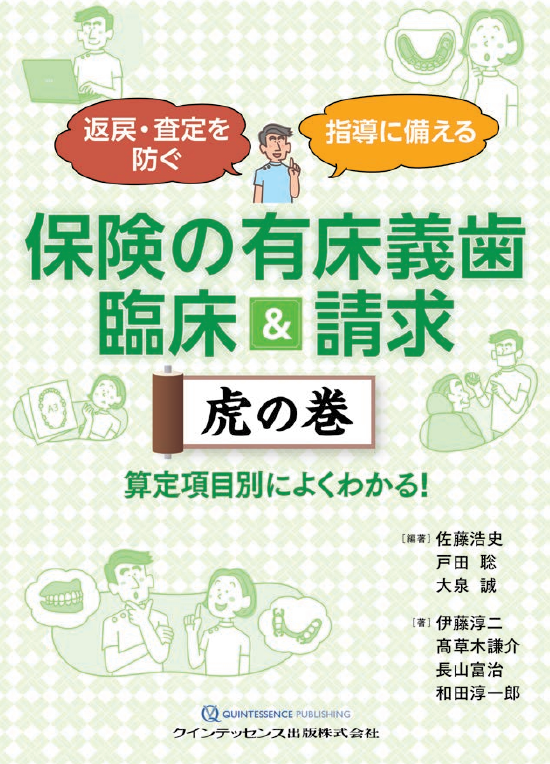
保険の有床義歯臨床&請求 虎の巻
当分野の和田助教,髙草木助教,長山医員,佐藤浩史先生(非常勤講師)の執筆した書籍が刊行されました.
有床義歯の保険点数の解説に加え,義歯製作についての基礎知識について解説しています.
困った時に手元に置いてすぐに活用できるような書籍を目指しました.
ご一読ください!
歯科技工別冊 はじめる!使いこなす! 3Dプリンターの基礎と臨床
当分野の髙市助教の上梓した記事が,歯科技工別冊 はじめる!使いこなす! 3Dプリンターの基礎と臨床に掲載されました.
第1章 3Dプリンターの基礎
造形角度が適合精度に及ぼす影響

ザ・クインテッセンス 2022年8月号
当分野の和田助教,若林教授が歯周病学分野の水谷助教と上梓した記事が,ザ・クインテッセンス2022年8・10・12月号,ならびに2023年2月号に掲載されました.
特集 ペリオ×パーシャルデンチャー
支台歯をどう守り,どう活用するのか
第1回 補綴治療を前提とした歯周治療(2022年8月号)
第2回 支台歯を保護・活用するための義歯設計(2022年10月号)
第3回 弱体化した支台歯への補綴的アプローチ(2022年12月号)
第4回 補綴治療後のフォローアップ(2023年2月号)
歯界展望 2022年4月号・5月号
当分野の和田助教,若林教授の上梓した記事が,歯科医展望2022年4月号と5月号に掲載されました.
特別企画
欠損補綴における補綴装置および支台歯の選択―――ブリッジと部分床義歯の比較
前編 ブリッジ治療における支台歯選択について (4月号)
後編 部分床義歯治療における支台歯選択について (5月号)
和田淳一郎,若林則幸
当分野の和田助教,髙市助教,若林教授の上梓した記事が,日本歯科評論(The Nippon Dental Review)2022年1月号に掲載されました.
Clinical Review
磁性アタッチメントの臨床手技-保険収載を機に,その有用性を再確認しよう
和田淳一郎,髙市敦士,若林則幸
当分野村上助教が「デンチャー臨床“なるほど”攻略ガイド
」にて,ノンメタルクラスプデンチャーの適応症に関して解説しております.
デンチャー臨床“なるほど”攻略ガイド
『ノンメタルクラスプデンチャーの適応症と禁忌症例を教えてください』(村上奈津子)
月刊「歯界展望」別冊 はじめての部分床義歯 (医歯薬出版)
松田謙一,荻野洋一郎,兒玉直紀,和田 淳一郎 編
当分野の和田淳一郎助教をはじめ,新井助教,稲用助教,高草木特任助教が上梓いたしました.
【出版社の内容紹介】
一般的な治療としてニーズが高まる”部分床義歯臨床”への不安と悩みを確実に減らし.治療を成功へと導く一冊!
●若手臨床家必携の部分床義歯治療の入門書です!
●「はじめて部分床義歯症例を担当する際に,何を知っておくべきか?」をメインテーマに据え,豊富な写真とイラストで分かりやすく解説!
●東西問わず大学の補綴科で義歯臨床を学んだ若手臨床家による,義歯臨床を成功させるために共通して重要だと考えられるポイントを治療工程ごとに収載

当分野の和田助教,若林教授が,ザ・クインテッセンス 2021年3月号から4ヶ月間の短期連載で,咬合挙上について解説しています.
巻頭特集
『咬合挙上の今あるエビデンスと臨床手技教えます “うまくいく”を“たまたま”から“確実”にするために』
第1回 咬合挙上を理解するための重要な知識の整理
(和田淳一郎,若林則幸)
(記事より引用)
補綴分野,とくに咬合再構成の際に議論されることが多い事項として咬合高径が挙げられる.その挙上の是非にはじまり,挙上をする場合の評価や検査,診断法,また実際の挙上法など,いずれも多くの研究者・臨床家が過去に俎上に挙げてきた.しかしながら,咬合を取り巻く諸々の事項がそうであるように,咬合高径の諸事項に関しても確固たるエビデンスは求めづらく,統一された意見も少ないことから,画一的な臨床手技がないように思われる.そこで,本連載では,咬合高径の評価,挙上方を,現在までの文献と臨床でひも解き,日常臨床で悩む臨床家読者へのヒントを提供したい.
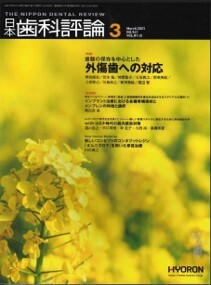
当分野の村上助教,笛木准教授,谷田部臨床教授,若林教授が「臨床のヒント」で,ノンメタルクラスプデンチャーの特徴と適応に関して,従来のメタルクラスプデンチャーと比較しながら症例を交えながら解説しております.
臨床のヒント
『ノンメタルクラスプデンチャーの使いどころ』
(村上奈津子,笛木賢治.谷田部 優.若林則幸)

当分野の村上助教,山崎特任助教,若林教授が,特集記事で補綴領域における有限要素解析の応用に関して,当分野の研究,特に歯科理工系の補綴研究における実例をもとに,その活用方法について寄稿しております
特集「各種シミュレーション技術の歯科応用」
『補綴領域における有限要素の応用』
(村上奈津子,山﨑俊輝,若林則幸)
(記事より引用)
有限要素解析は,コンピュータ上に構築した形態モ デルに力学的な条件を与え,その内部の物理データを計算するための手法の一つです.この手法を用いることで,応力や歪みなどの物理データをモデル上で色分けして表示し,モデルの形態の変化を視覚的に捉えることができます.補綴装置とその材料の破壊や変形のリスクを予測することに適しており,著者らの研究内容とともにその活用方法を解説する.
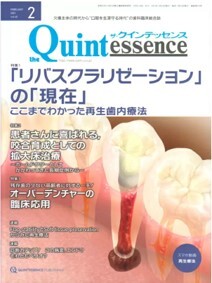
ザ・クインテッセンス 2021年2月号のReading Matters「医局紹介:研究プロジェクトの精鋭たち」において,当分野が紹介されました.
医局紹介:研究プロジェクトの精鋭たち
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科部分床義歯補綴学分野 (新井祐貴,若林則幸)
(記事より引用)
学生の教育に重点を置くのが教室の方針であり,歯学科を中心に口腔保健衛生学専攻,口腔保健工学専攻への学生教育に加え,さまざまな卒後研修を担当している.昨年は「部分床義歯補綴学」を同期型のオンライン授業により実施するなかで,グループ学習によるアクティブラーニングを全てオンラインで行なった.卒後研修でもオンラインによる症例検討会・義歯設計演習を行うなど,受講者から好評を得ている.
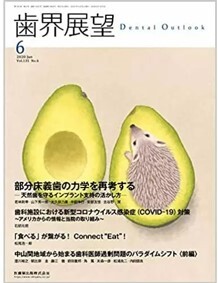
当分野若林教授が特集『部分床義歯の力学を再考する』の冒頭で,我が国での部分床義歯の重要性,インプラントを支持に利用した部分床義歯についての見解について,寄稿しております.
巻頭特集
『部分床義歯の力学を再考する ―天然歯を守るインプラント支持の活かし方―』 (若林則幸,山下秀一郎,大久保力廣,中居伸行,安部有佳,古谷野潔)
(記事より引用)
インプラント支持を利用した部分床義歯のニーズは,これからさらに高まると考えられています.そこで,こうした活用法は,現在どのような意義があると考えられており,これからどのように役立てていくのかなど,研究・臨床をもとにしたさまざまな観点から,提案をいただいています.明日からの臨床にお役立てください.
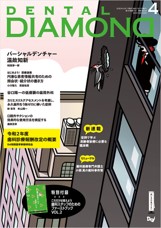
当分野助教の和田が巻頭特集にて,部分床義歯の基本的事項について解説しております.
巻頭特集
『パーシャルデンチャー 温故知新』 (和田淳一郎)
(記事より引用)
近年、インプラントを利用したパーシャルデンチャーやノンメタルクラスプデンチャーが注目を 集めているが、長期予後のためにはパーシャルデンチャーにおける症例の捉え方と設計の基本を身につけておくことが重要である。
本特集では、残存歯の保護を念頭におき、設計の基本を振り返りながら、さまざまな欠損形態に対応するために必要な考え方や前処置のコツ、印象採得や咬合採得のポイントなどについて解説いただく。
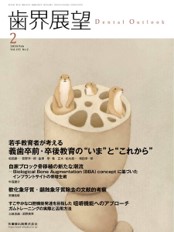
当分野助教の和田が,義歯卒前・卒後教育についての座談会に参加した模様が紹介されました.
座談会
『若手教育者が考える 義歯卒前・卒後教育の“いま”と“これから”』 (和田淳一郎)
(記事より引用)
本特集は『座談会 若手教育者が考える義歯卒前・卒後教育の“いま”と“これから”』です.社会の高齢化に伴い学部教育の変化として,義歯教育時間数や臨床実習でのケース数が減少し,卒業後に義歯製作するための知識が不足し,特に技工操作を行わなくなっているとの実態があるようです.そこでますます重要性が増す卒後教育の重要なツールの一つとして,オンラインでのコミュニティなどの活用を指摘しています.ご一読をお薦めします.
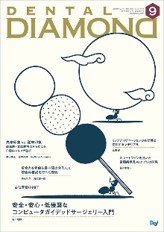
当分野非常勤講師の葉山,教授の若林が「Dd“IOS”セミナー」にて,光学印象について解説しております.
Dd“IOS”セミナー
『光学印象 vs. 従来印象 臨床的・文献的視点から捉える口腔内スキャナ選び』 (葉山博工・若林則幸)
(記事より引用)
近年、歯科医療のデジタル化が進むなかで、メーカー各社より高精度の口腔内スキャナが上市されている。導入を検討している歯科医師にとっては、従来印象と比較して印象精度に差はないのか、どのような口腔内スキャナを選ぶべきなのかは気になるポイントだと思われる。本特集では、臨床的・文献的視点から光学印象と従来印象の比較や各種口腔内スキャナの特徴について解説いただく。