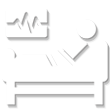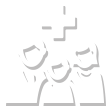市民公開講座 東京科学大学病院と学ぶ「医療の最前線」第1回オンラインセミナー参加者募集(参加費無料・事前申込要)5月20日17時スタート(Science Tokyo 設立記念イベント)
5月20日17:00~オンラインセミナーを無料開催
東京科学大学と学ぶ「医療の最前線」
(Science Tokyo 設立記念イベント)
東京科学大学病院支援基金は、先進的医療の開発推進、診療体制の充実、病院施設・環境の整備を通じて、より良い患者サービスの提供を目指しています。そしてこの度、同基金では、最先端の医学・医療研究や最新の診断技術や治療法を、広く社会に理解していただくために、市民公開講座を定期的に2025 年度は6 回、オンラインまたは会場で開催することに致しました。参加費は無料で、どなたでもご参加できます。最先端の医学研究や多くの皆様が気になる疾患に関する診断・治療法について、東京科学大学病院と一緒に学びませんか?
| 開催日時 | 2025年5月20日 17:00~18:00 |
|---|---|
| 問合せ先 | pr-hosp.adm@tmd.ac.jp(東京科学大学病院 事務部 病院総務課 総務グループ) |
| 申込方法 |

●参加費無料 お申し込みは、右の二次元バーコードもしくは、以下URL よりご確認お願いいたします。 |
講師の石田 岳史先生、戸原 玄先生にインタビュー
多くの皆様に、東京科学大学病院の特色ある医療についてご理解いただくために、第1回の講師である、東京科学大学病院 総合診療科 教授 石田 岳史 先生と、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 教授 戸原 玄 先生に、お話を伺いました。それぞれの講演テーマや、先生ご自身の健康について、伺っております。
-

第1回講師
東京科学大学病院 総合診療科 教授 石田 岳史 先生
テーマ:医療のかしこい使い方 ~新たな地域医療構想を踏まえて~プロフィール
東京科学大学病院 総合診療科 教授 石田 岳史 先生1993年自治医科大学卒。日本内科学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本循環器学会
日本心臓リハビリテーション学会、日本心不全学会、日本臨床生理学会などに所属。日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本循環器学会専門医。- 【質問1】 総合診療科とはどんな診療科で、どんな症状や疾患を抱えた患者さんが受診していますか?
-
石田 岳史 先生 当院の総合診療科は完全紹介制となっております。かかりつけ医や他の医療機関から、診断が困難な症例をご紹介いただいています。主に、不明熱(原因が特定できない発熱)、原発不明がん、複数の臓器に障害があり、単一の診療科では対応が難しい症例などを診療していますが、セカンドオピニオンのご相談も受け付けています。また、ポリファーマシー(服用薬の種類が多くお困りの方)や、慢性疾患の薬をいつまで内服し続けるべきかといったご相談にも対応しており、患者さんと話し合いながら、「明日からの治療」を一緒に考えています。
- 【質問2】 先生が、総合診療科をご専門にしようと選んだきっかけはどんなことだったのでしょうか?
-
石田 岳史 先生 日本中、そして世界中どこへ行っても求められるスキルであることが、総合診療の大きな魅力です。へき地医療にも携わってきましたが、目の前の患者さんと向き合い、視診(見て)、聴診(聞いて)、触診(触れて)、そして簡便な検査と知識を総動員して正確に診断することに、大きなやりがいを感じています。フランス語に「ブリコラージュ(あり合わせのもので工夫して物を作る)」という言葉がありますが、まさにその精神で、できない理由を探すのではなく、今ある資源を最大限に活かして挑むことこそが、総合診療の醍醐味だと感じています。COVID-19への対応は、その代表的な実践例と言えるかもしれません。
- 【質問3】 総合診療科のやりがい、「この診療科を選んでよかった!」と実感するのはどんな時でしょうか?
-
石田 岳史 先生 診断が難しい患者さんと向き合い、文献を調べたり、他の専門家とディスカッションを重ねたりしながら、確定診断にたどり着けたときには、ほっとすると同時に、大きなやりがいを感じます。そして、患者さんから感謝の言葉をいただけたときには、「総合診療医になって本当によかった」と心から思います。
- 【質問4】 どのような背景から、今回の講演テーマ「医療のかしこい使い方 ~新たな地域医療構想を踏まえて~」をお考えになりましたか?
-
石田 岳史 先生 いわゆる「2040年問題」とは、少子高齢化に伴う働き手の減少と、それに起因する財源不足の問題です。しかし、どのような時代であっても、国民には適切な医療を受ける権利があります。一方で、限られた医療資源は、すべての人に対して公正かつ効果的に活用されなければなりません。そのためには、医療従事者だけでなく、全国民一人ひとりが「医療の利用のしかた」について理解を深めることが求められます。今回の講演が、その気づきのきっかけとなれば幸いです。
- 【質問5】 石田先生の健康法・ストレス解消法について、教えてください。
-
石田 岳史 先生 私の健康法は「歩くこと」です。通勤では座らず、エスカレーターも使いません。旅先の不慣れな土地でも、タクシーの利用は最小限にとどめています。ストレス解消法は「グルメ」ですね。日常よりも少し贅沢な食事を楽しむこと、とくに異業種で活躍されている方々との会食は、ストレス解消になるだけでなく、良い刺激にもなり、明日への活力の源になります。そのときのアルコールは、潤滑油になるかもしれませんね(笑)。
-

第1回講師
東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 教授 戸原 玄 先生
テーマ:これからの摂食嚥下リハビリテーションプロフィール
東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 教授 戸原 玄 先生1997年、東京医科歯科大学歯学部歯学科卒。同大学院、藤田保衛大学医学部リハビリテーション医学講座研究生、ジョンホプキンス大学医学部リハビリテーション科研究生などを経て、現在は高齢者や在宅における歯科医療のリーダーとして、革新的な臨床活動を行う だけではなく、仕組みやフィールド含めた環境整備、エビデンス創出、機器開発、国内外の後進育成などを数多くの活動を実践中。
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士
日本老年医科歯科学会 認定医老年歯科専門医・指導医・摂食機能療法専門歯科医師- 【質問1】 摂食嚥下リハビリテーション科とはどんな診療科で、どんな症状や疾患を抱えた患者さんが受診していますか?
-
戸原 玄 先生 口から食事をしているけれどもむせなどでうまく食べられない方、もしくは胃瘻などで栄養を摂取しているがまた口から食べられるようになりたい方が多いです。
その他、のどを手術で切除して声が出せなくなった方へのリハビリ用の機器も作成しています。 - 【質問2】 先生方が摂食嚥下リハビリテーション科をご専門にしようと選んだきっかけはどんなことだったのでしょうか?
-
戸原 玄 先生 正直にいうと、自分が大学院生のころの教授やるように言われたというのが理由なのですが、それを本当にやろうと思ったのは国内外留学後一人でやりはじめたところ結果が出始めたからです。25年くらい前だったと思います。
- 【質問3】 摂食嚥下リハビリテーション科 のやりがい、「この診療科を選んでよかった!」と実感するのはどんな時でしょうか??
-
戸原 玄 先生 患者さんやご家族が喜んでいる顔をみたときです。
その他、後輩が成長して必ずしも自分自身がかかわらなくても結果が出たとき、もしくは一人前になったような姿を目の当たりにしたときです。 - 【質問4】 どのような背景から、今回の講演テーマ「これからの摂食嚥下リハビリテーション」をお考えになりましたか?
-
戸原 玄 先生 摂食嚥下リハというと、嚥下の検査をして嚥下の訓練をする、というイメージしかおそらく持っていただいていないと思います。
そういうこと以外に実は色々とやりようがあるということをしっていただければありがたいです。 - 【質問5】 戸原先生の健康法・ストレス解消法について、教えてください。
-
戸原 玄 先生 全然関係ない本を読む、実家の庭の木を切って畑を作る(収穫して何か作る、例えば「柚子胡椒」など)、スーパー銭湯行く、子供と出かける、などです。
東京科学大学病院支援基金について

本学は、先端的医療の研究開発や診療体制の充実、医療人材の育成などを通じて社会に貢献しています。
いただきましたご芳志は診療体制の充実や人材教育、研究開発に活用し、未来の医療の発展に役立てます。
東京科学大学病院支援基金への皆様のご支援をお願い申し上げます。
チラシダウンロード
東京科学大学病院支援基金市民公開講座は、人と社会に健康と安心をお届けするために、2026年3月まで定期的に開催します。詳細は下記のPDFをご覧ください。