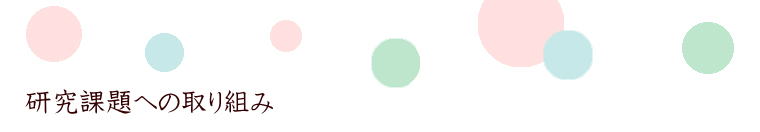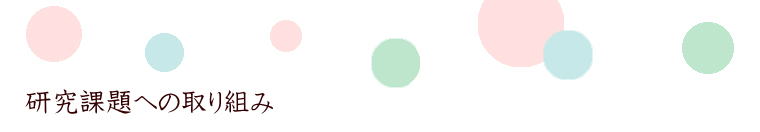|
義歯装着者の咀嚼能力の評価
う蝕や歯周病などにより歯が失われると,「よく噛めない」,「見た目が悪い」,「話しにくい」,「かみ合わせが不安定」など口腔の機能にさまざまな障害を生じます.部分床義歯を用いた補綴治療は,歯の喪失により低下した口腔機能の回復を目的の一つとしています.補綴治療の効果を評価するためには,口腔機能を客観的に測る必要があります.
私たちは,新たに開発した2色のワックスを用いて,義歯でどの程度噛めるかを簡単に測ることができるシステムを開発し,噛む能力にどのような因子が関わっているのか研究しています(※).その成果は,よく噛める部分床義歯の設計に役立てられます.
(研究代表者:笛木賢治))
生体と義歯の応力解析による設計の最適化
部分床義歯は,失われた歯の代わりに残っている歯や顎骨などと協調して働きます.しかし,咀嚼(そしゃく)機能の回復を十分に達成するためには,義歯が口腔内の様々な組織と良好な「力関係」を実現できるように設計されなければなりません.そうでなければ,一部の歯や粘膜に大きな「負担過重」を生じたり,義歯の破損を引き起こします.
生体と生体材料にかかる力の負担は,それぞれの内部に生じる「応力」や「歪み」を分析することで正確に推定できます.この分析は,三次元的な力学モデルを用いたシミュレーション解析により行います.
私たちは,とくにモデルによる演算が困難な接触問題,粘弾性,疲労,材料非線形など難度の高い非線形解析に重点的に取り組んでおり,複雑な歯の動きや粘膜内部の微小歪みの分析を世界に先駆けて発表しています.その結果は,歯や顎骨を守る安全で耐久性の高い義歯の設計と新しい材料の開発に活用されます.
(研究代表者:若林則幸)
短縮歯列の治療効果についての多施設共同研究
臼歯(奥歯)を失うと噛む能力が低下することはよく知られています.しかし,失われた臼歯が1,2本程度に限局している(短縮歯列)ケースでは,噛むことにそれほど困らない場合もあります.ヨーロッパでは,このようなケースに対して部分床義歯による治療を積極的にする必要はないという考え方が広く支持されていますが,一方,日本においては,本当に義歯による治療が必要ないのかについて未だ議論がなされています.
私たちは,短縮歯列を有する患者様を対象として,部分床義歯とインプラント義歯の治療効果を明らかにするために,国内7大学(東北大学,昭和大学,東京医科歯科大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,九州大学)共同で臨床研究を行っています(※).その成果は,今後,歯科臨床における短縮歯列コンセプトの適用に役立てられます.
(研究代表者:五十嵐順正)
|