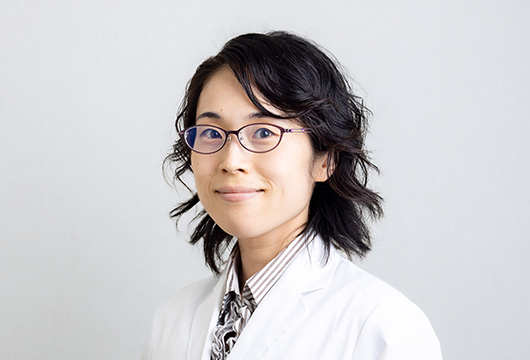
当制度に申請した理由(着任への想い、どのようなスタンスやマインドでダイバーシティ推進に携わろうとしているか、キャリアアップに向けた意欲など)を教えてください。
私は初期研修修了直前に結婚し、脳神経外科医としてのキャリアが始まってすぐに妊娠と出産を経験しました。子供2人を育てながら12年以上、妊娠中の体調不良や育児と常勤勤務の両立において、さまざまな悩みや苦しみ、家族や職場との対話を重ねてきました。辞めたいと思ったことは数え切れませんが、なんとか踏みとどまり、2020年に助教として招聘いただき、今に至ります。
日本脳神経外科学会における女性医師の割合は7.13%(2023年)と少なく、上位職・管理職にいる女性はさらに少ないのが現状です。ハラスメントや差別がない場合でも、脳神経外科医の常勤勤務は非常に忙しいため、育児との両立に疲れて離職してしまう女性も少なくありません。育児との両立で苦しい時期があっても、努力は報われること、そして次世代の育成をしながらでもキャリアアップが可能であることを、私自身の経験を通じて示すために、本制度に申請しました。
ご自身のお仕事の内容とその魅力について教えてください。
2021年から当科において、もやもや病の診療研究責任者を担当しています。もやもや病は厚生労働省指定の難病で、有病率は10万人に数人とされています。当院は1980年代からもやもや病の診療に力を注いでおり、通算通院患者は1,000人を超え、現在400人以上の患者さんが通院中です。毎月2~3人の新規患者さんが受診し、外来診療や手術に加え、大学院生や若手医師のもやもや病に関連した臨床研究指導も行っています。
もやもや病の患者さんはお子さんや30~40代の若い方が多く、治癒することのない難病であるため、就学や就労、妊娠・出産といったライフイベントにおいても長いお付き合いが必要です。女性患者さんが多く、女性・母親であることが役立つと思う場面も多々あります。自分の判断が患者さんの長い人生にどのように影響するかを考えると不安になることもありますが、それだけに、より良い判断を下すために、ますます臨床研究に励もうとやりがいも感じます。
研究分野としては、脳画像、特にMRIを得意としています。脳MRIは、放射線被曝なく生きたヒトの脳を外から見ることができる奥深い技術です。脳の形態や血管、脳血流画像は精細で美しく、脳の機能や代謝をみることもできます。私が医学部を志した理由は脳が生み出す心の不思議に惹かれたからでしたが、心は脳のどこにあるのか?も、MRIの研究で明らかになりつつあります。
キャリアアップ教員に就いたことで、ご自身や周囲で変化したこと等があれば教えてください。
全方向からとめどなく降り注ぐ業務に疲弊しきっていた頃、採択通知をいただきました。これまでの成果を認めていただけたことは大変嬉しく、さらにキャリアアップに邁進したいという意欲が増しました。また、普段残業や当直、出張で負担をかけている家族も大変喜んでくれました。日頃の協力に報いることができたことも、大変嬉しいことでした。
当制度に期待すること、ご要望等はありますか。
日本の医療界やアカデミアには非常に大きなジェンダーギャップが存在しており、当制度のような積極的な差別是正措置は、その是正に有益であることは間違いありません。しかし、女性であるだけでキャリアアップしやすい制度は真の平等とは言えません。当制度はジェンダーギャップ縮小のための一時的な措置であってほしいと考えています。そして、当制度によって女性が上位職に就くことが当たり前になった後は、制度なしでも多くの女性が自然とキャリアアップできるようになってほしいと願っています。
ダイバーシティ推進は目的ではなく、より高い成果を目指すための手段であるべきです。ビジネス界では、組織のダイバーシティが創造性、満足度、パフォーマンスを向上させることが既に示されています。当制度について、男性や他のダイバーシティに配慮が必要な方々にも理解を得られるよう、当制度を通じて支援者がどのように成長、成果を上げ、大学に貢献したかを積極的に明示していただければと思います。
今後の目標(どのような女性リーダーになろうとしているか、研究者・医師・歯科医師・教育者としての抱負など)を教えてください。
これから受講するリーダーシップ研修を通じて、ビジョン型リーダーシップやコーチ型リーダーシップを磨いていければと考えています。
臨床研究医としては、多忙な日々の中でも患者さんと向き合う時間を大切にし、手術の技術を磨き、日々の疑問を臨床研究に結びつけ、その成果を患者さんに還元できるよう引き続き努力していきます。



