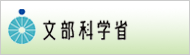News & Topics
- 2016年9月20日
- 研究成果報告書を掲載しました。
- 2015年2月28日
- 『シナプス病態』の冬の班会議が開催されました。(於:文部科学省共済組合箱根宿泊所 四季の湯強羅静雲荘)、開催日: 2月28日、3月1日)(写真を見る)
- 2015年1月29日
- <プレスリリース>公募班員・河原行郎(大阪大学医学系研究科神経遺伝子学・教授)らのグループは、神経変性疾患の発症と深く関連するタンパク質TDP-43の断片化メカニズムとその生理的意義を解明しました。ALSやFTLDなどでは、TDP-43が断片化・リン酸化などの修飾を受け、変性神経細胞内に蓄積しています。中でも、約25kDaのC末端断片 (CTF25)の蓄積が顕著です。また、培養細胞や動物モデルでTDP-43を過剰に発現させると、CTF25が観察されます。しかし、正確な切断点、切断を担う酵素、切断の生物学的意義の詳細については不明でした。今回私達は、小胞体に局在するカスパーゼ4が、174番目のアスパラギン酸残基を認識・切断することによりCTF25が産生されることを突き止めました。本切断は、TDP-43のクリアランス開始のシグナルとなっており、この切断を阻止すると、クリアランス速度が著しく遅くなり、過剰となった完全長TDP-43を介して、細胞死が増悪することも明らかにしました。これらの結果から、CTF25を産生する切断は、TDP-43量を一定に制御し、細胞死を回避するための機構だと考えられました。本研究成果は、Nature Communications誌に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年12月19日
- <プレスリリース>公募班員・星野幹雄(国立精神神経医療研究センター神経研究所・部長)らのグループは、自閉症スペクトラム障害、統合失調症、ADHD、薬物依存などの精神疾患やてんかんに広く関連するAUTS2(Autism Susceptibility Candidate 2)遺伝子の働きを、初めて明らかにしました。この遺伝子のコードするAUTS2蛋白質は長らく核蛋白質として機能すると考えられてきていましたが、その分子機能は不明でした。星野らは、厳密な細胞分画実験と免疫染色によって、AUTS2が神経細胞の細胞質、特に神経突起にも多く存在し、RhoファミリーG蛋白質であるRac1やCdc42の活性を正・負に制御することで、神経細胞のアクチン細胞骨格系を再構成することを見いだしました。さらに、ノックアウトマウスの解析から、AUTS2が神経細胞の移動や突起伸長の促進作用を介して、神経ネットワーク形成に関与していることも明らかにしました。この研究は、AUTS2遺伝子異常によるヒト精神疾患の病態の理解につながると考えられます。本研究成果は、Cell Reports誌に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年12月18日
- <プレスリリース>林 康紀シニアティームリーダー(理化学研究所脳科学総合研究センター、兼、埼玉大学脳末梢科学研究センター)らは山口大学医学部、横浜市立大学医学部と共同研究で、これまで学習・記憶の分子メカニズムの鍵と考えられてきた現象が、実はそうではないという反証を行いました。脳の神経細胞の結合であるシナプスの間はグルタミン酸(味の素と同じ物質)によって伝達が行われています。これを担うのが、グルタミン酸受容体です。これまで学習に伴いグルタミン酸受容体にリン酸基が結合すること(リン酸化)により受容体活性が上昇し、シナプス伝達効率が向上するというモデルが幅広く受け入れられてきました。ところが、これまでどれくらいのタンパク質がリン酸化を受けているかを調べる方法がなく、完璧な証明はなされてきませんでした。林シニアティームリーダーらは最近、広島大学の木下准教授らによって開発されたPhos-tag SDS-PAGEを用いることにより、グルタミン酸受容体リン酸化の定量を行いました。その結果、グルタミン酸受容体のリン酸化は非常に少なく、これまでのモデルが成り立たないことが見いだされました。林シニアティームリーダーらは新たなモデルを提唱するとともに、これまでよく知られてきたリン酸化反応でも実際にリン酸化を受けているタンパク質を定量することの重要性を示唆しました。この結果は米国学術誌“Neuron” (細川ら2014年12月18日オンライン発行)に発表されました。
- 2014年12月13日
- 『包括型脳科学研究推進支援ネットワーク』冬のシンポジウムの中で『山森・岡澤・能瀬領域「大脳新皮質構築」「シナプス病態」「メゾ神経回路」3領域合同公開シンポジウム』が開催されました(於:ホテル東京ガーデンパレス、高千穂A)。(プログラムを見る)
- 2014年12月11日
- 『包括型脳科学研究推進支援ネットワーク』冬のシンポジウムの中で『岡澤・門松・喜田・高橋・池中領域「精神神経疾患研究の現状と展望:新学術5領域の相互理解・連携を目指して」』が開催されました(於:東京医科歯科大学M&Dタワー、鈴木章夫記念講堂)。(プログラムを見る)
- 2014年12月8日
- <プレスリリース>公募班員・深田優子(生理学研究所・准教授)らの研究グループは、北海道大学医学部、Erasmus大学(オランダ)および東京大学の研究グループとの共同研究による成果を生理学研究所からプレスリリースしました。遺伝性てんかんのひとつである常染色体優性外側側頭葉てんかん(Autosomal Dominant Lateral Temporal Lobe Epilepsy:ADLTE)の原因が、変異LGI1タンパク質の構造異常とADAM22受容体との結合低下に基づくことを見出しました。そして、化学シャペロンという薬剤で構造異常を修復することにより、てんかんが軽減することをマウスモデルで明らかにしました。本研究結果は、Nature Medicine誌(2014年12月8日電子版)に掲載されました。(詳しい内容を見る
 )
)
- 2014年11月21日
- <プレスリリース>計画班員・貫名信行(順天堂大学大学院医学研究科・客員教授)らの研究グループは、線条体の抑制性投射神経細胞である中型有棘神経細胞が、無髄神経線維束を形成していることを初めて明らかにしました。これまで大脳ではいくつかの無髄神経の存在がわかっていますが、すべて興奮性を主体とした線維束を形成しており、抑制性のみで形成されたものは見つかっていませんでした。興味深いことに、線条体投射神経では、有髄神経のランビエ絞輪という部位に限局しているはずの電位依存性ナトリウムチャネルβ4サブユニット(β4)が、軸索全体に均一に分布していることを発見しました。 さらにβ4の発現を欠損したマウスの線条体では、神経の電気的活動が障害されることから、β4がこの無髄神経の正常な機能に不可欠であることを明らかにしました。本研究成果は、Nature Communications誌に掲載されました。(詳しい内容を見る
 )
)
- 2014年10月14日
- <プレスリリース>公募班員・山梨裕司(東京大学医科学研究所・教授)らの研究グループは、これまでに神経筋接合部の形成に必須のタンパク質としてDok-7を発見し、それが、MuSKというタンパク質(リン酸化酵素)の活性化因子であること解明しています(Science, 312:1802-05; Science Signal., 2:ra7)。興味深いことに、MuSKにはAgrinと言う別の活性化因子の存在が古くから知られており、両者の違いが不明でした。今回、同研究グループはDok-7を多量に産生することでMuSKの活性化を恒常的に増強するマウスを作出し、そのマウスにAgrin欠損を導入したところ、胎仔期に形成された神経筋接合部が誕生後の数週間で消失することを発見しました。この事実は、胎仔期のAgrin機能がDok-7の発現増強によるMuSKの活性化で補えるのに対して、生まれた後のAgrinはMuSK活性化以外の、Dok-7では代替不可能な仕組みで神経筋接合部を守っていることを意味します。この発見は、我々が神経筋接合部をどのようにして守っているのかを理解するために重要であると共に、生まれた後に発症する多くの神経・筋疾患の理解につながる知見です。これらの成果はProc. Natl. Acad. Sci. USA誌に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年10月9日
- <プレスリリース>計画班員・貫名信行(順天堂大学大学院医学研究科・客員教授)らの研究グループは、選択的オートファジーに関わる蛋白質p62のハンチントン病モデルマウスにおける機能を検討するため、ハンチントン病モデルマウスにおいてp62を欠損した状態を引き起こし、その影響を検討しました。本来分解系を制御しているp62が欠損した場合、病態の増悪が予想されるはずが、p62 欠損によってハンチントン病において集積する核内封入体が減少し、細胞質の封入体の増加を認め、寿命が延長することを見出しました。この逆説的な現象は細胞質で働くポリグルタミン病の異常タンパク質の分解機構が障害されたため、細胞質で主に蓄積したため、核内での影響が少なくなり引き起こされたものと考えられました。この結果は核内封入体が病態に大きく影響していることを示しており、治療には核内移行を減少させることの重要さを示しました。これらの結果はHum Mol Genetに報告されました。
- 2014年9月30日
- <プレスリリース>計画班員・貫名信行(順天堂大学大学院医学研究科・客員教授)らの研究グループは、RNA結合蛋白質のmuscleblind-like 1 (MBNL-1)がCUGやCAGのリピートを含む変異RNAと結合することを示し、これらのMBNL-1と結合した変異RNAが核内に集積することを示しました。これによって変異RNAの遺伝子産物である蛋白質の産生が抑えられることがわかりました。この結果は遺伝子内のリピート伸長によって引き起こされるポリグルタミン病などのリピート関連疾患をその変異RNAからの蛋白質発現を抑えるという新たな治療の可能性を示しています。これらの結果は国際科学誌Human Molecular Geneticsに報告されました。
- 2014年9月19日
- <プレスリリース>公募班員・山梨裕司(東京大学医科学研究所・教授)らの研究グループは、これまでに神経筋接合部の形成に必須のタンパク質としてDok-7を、また、そのヒト遺伝子(DOK7)の異常による劣性遺伝病として神経筋接合部の形成不全を呈するDOK7型筋無力症を発見しています(Science, 312:1802-05; Science, 313:1975-78; Science Signal., 2:ra7)。一方、神経筋接合部の形成不全は筋無力症のみならず、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や加齢性筋肉減少症などの多様な神経筋疾患にも関与していますが、その治療標的としての可能性は不明でした。今回、同研究グループはマウスを用いた実験から、DOK7発現ベクターの投与により神経筋接合部を後天的に拡張できることを確認し、また、DOK7型筋無力症マウスへの投与によりその運動機能を改善し、生存期間を延長しました。さらに、筋ジストロフィーの一種を発症しているマウスにおいても類似の効果を実証しました。この発見は、DOK7遺伝子発現ベクターの投与による「神経筋接合部の形成増強治療(小さくなってしまったNMJを大きくする治療)」と言う全く新しい治療概念の創出を意味します。これらの成果はScience誌に掲載されました。(詳しい内容を見る
 )
)
- 2014年9月17日
- <プレスリリース>領域代表者・岡澤 均(東京医科歯科大学難治疾患研究所・教授、脳統合機能研究センター長)のグループは、東大・医科研などとの共同研究により、アルツハイマー病の発症前、凝集前の超早期病態の一端を解明しました。アルツハイマー病の治療開発においては、発症前の早期病態を解明することが現在の最重要課題とされています。最新の質量分析技術とスーパーコンピュータを用いたシステムズバイオロジーを駆使して、アルツハイマー病モデルマウスおよびアルツハイマー病患者脳のタンパク質を網羅的に解析し、発症前さらには老人班と呼ばれる異常タンパク質凝集が開始する前に、タンパク質リン酸化シグナルの異常が超早期病態として存在することを発見しました。明らかになった超早期のコア病態シグナルネットワークあるいはコア病態分子をターゲットとする治療法を本格的に開発することによってアルツハイマー病の進行を抑制し、治癒に導く治療法を開発できる可能性があります。この研究成果は、国際科学誌Human Molecular Geneticsに掲載されました。(詳しい内容を見る
 )
)
- 2014年8月28日
- <プレスリリース>計画班員・勝野雅央(名古屋大学大学院医学系研究科神経内科・准教授)らのグループは、pioglitazoneが神経変性疾患の一つである球脊髄性筋萎縮症(SBMA)の病態を抑止することを明らかにしました。SBMAはアンドロゲン受容体の遺伝子変異により運動ニューロンと骨格筋の変性を呈する神経筋疾患ですが、その細胞モデル・動物モデルおよび患者組織を用いた解析により、SBMAの運動ニューロンおよび骨格筋ではミトコンドリア生合成に必要な転写因子であるperoxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) の発現が減少していることが明らかとなりました。PPARγのアゴニストであるpioglitazoneを投与したところ、SBMAモデルマウスにおける運動ニューロン・骨格筋の変性が抑制され、運動機能が改善しました。また、pioglitazoneには様々な作用があるため、それを利用してSBMAの病態を解析したこところ、SBMAモデルマウスの脊髄、骨格筋においてミトコンドリア機能低下、酸化ストレス上昇、グリア細胞の形態・機能変化およびNFκBシグナルの活性化などの異常がみられ、pioglitazoneがそれらを改善させることが明らかとなりました。NFκBシグナルがSBMAなどの神経変性疾患において治療の標的分子となることが示され、またSBMAでは運動ニューロンのみならず骨格筋も治療標的となる可能性が示唆されました。本研究成果はHuman Molecular Genetics誌に掲載されました。
- 2014年7月29日
- <プレスリリース>領域代表者・岡澤 均(東京医科歯科大学難治疾患研究所・教授、脳統合機能研究センター長)のグループは、ドイツのマックス・プランク研究所などとの共同研究により、PQBP1遺伝子変異が小頭症を引き起こすメカニズムを明らかにしました。遺伝的な小頭症は3~5万人に一人の確率で生じ、脳のサイズが小さく知的障害を伴うことが多い病気です。PQBP1は小頭症の原因遺伝子として知られますが、遺伝子変異がどのようなメカニズムで小頭症につながるのかは明らかではありませんでした。今回、脳を作るもととなる神経幹細胞において特異的にPQBP1遺伝子を発現しない小頭症モデルマウスを作成しました。この小頭症モデルマウスでは胎児の脳形成期における細胞周期時間が異常に延長していることが分かりました。さらに、PQBP1は、間接的に結合しているAPC4の減少により細胞周期延長に貢献していることも判明しました。また、PQBP1欠損による神経幹細胞の細胞増殖抑制及び大脳皮質形成はAPC4を補うことにより回復しました。さらに、今回作成したPQBP1欠損マウスを妊娠中の母マウスへAAVベクターを腹腔注射してPQBP1を補充すると、生後の脳サイズが回復し、行動解析でも学習能力など知的障害関連の症状が改善しました。本研究成果は、人為的に脳サイズを調節することが可能であることを証明し、遺伝的な脳サイズ・知能の障害を改善しうる治療法への道筋を示したものです。これらの結果はMolecular Psychiatryに報告されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年7月23日
- <プレスリリース>計画班員・岩坪威(東京大学大学院医学研究科・教授)らの研究グループは、アルツハイマー病治療薬として開発されているフェニルイミダゾール骨格を持つγセクレターゼ修飾薬がγセクレターゼの活性中心サブユニットであるプレセニリンの細胞外領域に結合し、γセクレターゼを活性化していることを新たに発見しました。本成果は、フェニルイミダゾール型γセクレターゼ修飾薬の作動原理と作用部位を、世界で初めて同定したものです。今後、新たなアルツハイマー病の治療薬を化合物の構造や機能、そして標的分子との相互作用に基づいて合理的に設計する戦略に貢献し、その開発が加速することが期待されます。これらの結果はProc. Natl.Acad. Sci. USAに報告されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年7月23日
- <プレスリリース>公募班員・有賀純(長崎大医歯薬学総合研究科)らの研究グループは、海馬の抑制性ニューロンに発現する後シナプス膜タンパク質の1つ「ELFN1」が、代謝共役型グルタミン酸受容体の一つ「mGluR7」に結合して前シナプスへの集積を引き起こし、抑制性ニューロンのシナプス可塑性を制御していることを発見しました。ELFN1欠損マウスは、ヒトに触られるとてんかんのようなけいれん発作を示し、多動や警戒心の低下などの行動異常を示します。また、脳波をとってみると振幅の大きな異常な波が頻発することがわかり、脳の過活動が生じていました。研究グループはさらに、てんかんおよび多動症の患者さんのDNAを用いてELFN1の遺伝子変異を調べたところ、ELFN1の機能を損なう変異が一部の領域に集中して存在していることを発見しました。これらのことから、ELFN1は抑制性ニューロンへの適切なシナプス入力に不可欠のものであり、この遺伝子の変異がてんかん・多動症のような脳の興奮抑制バランスの乱れを背景とした病態に関係する可能性が示されました。本研究成果は、『Nature Communications』に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年6月27日
- <プレスリリース>計画班員・井上治久(京都大学iPS細胞研究所・教授)らのグループは、(1)ヒトiPS細胞由来のグリア系神経前駆細胞を筋萎縮性側索硬化症(ALS)のモデルマウスに移植することでマウスの生存期間が延長すること、(2) 移植細胞は多くがアストロサイトに分化し、神経栄養因子を増加させることで脊髄環境を改善することを示しました。これらの発見により、ALSの治療にiPS細胞が細胞源として有用であることが示されました。本成果はStem Cell Reportsのオンライン版に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年6月19日
- <プレスリリース>公募班員・河原行郎(大阪大学医学系研究科神経遺伝子学・教授)らのグループは、複数の神経変性疾患と関連するAtaxin-2の生理的機能を特定しました。もともとAtaxin-2は、遺伝性脊髄小脳変性症2型の原因遺伝子産物として同定され、Ataxin-2中のポリグルタミン鎖が異常伸長しています。また、最近では、同鎖の中等度伸長が、ALSの発症を高めることも知られています。しかし、Ataxin-2の機能の詳細については不明でした。今回私達は、PAR-CLIP法と呼ばれる手法を用いて、Ataxin-2の標的RNAを網羅的に決定することに成功しました。その結果、Ataxin-2が、主にmRNAの3’非翻訳領域に存在するウリジンに富んだ配列を認識し、直接結合することを発見しました。この中には、AU-rich elementと呼ばれるmRNAの安定性を規定する既知の配列も含まれており、Ataxin-2が、標的mRNAの安定性を促進することが分かりました。更に、ポリグルタミン鎖の伸長が、本機能を減弱させることも判明しました。本研究成果は、Molecular Cell誌に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年4月30日
- <プレスリリース>領域代表者・岡澤 均(東京医科歯科大学難治疾患研究所・教授)のグループは、富山大学薬学部構造生物学・水口峰之教授との共同研究により、PQBP1遺伝子変異による知的障害の病態分子メカニズムを明らかにしました。PQBP1は知的障害の主要な原因遺伝子として、また神経変性疾患にも関与する病態分子として知られますが、遺伝子変異がどのような分子機能変化を起こして知的障害につながるのかは明らかではありませんでした。今回、PQBP1タンパク質の立体構造をX線結晶構造解析によって決定し、PQBP1のYxxPxxVL配列(YxxPxxVLモチーフ)が、PQBP1とRNAスプライシング因子であるU5-15kDタンパク質の結合に必須であること、YxxPxxVLモチーフが知的障害の原因となるPQBP1変異体では全例欠損していることを発見しました。したがって、PQBP1遺伝子変異に伴う知的障害は、RNAスプライシングにおいてPQBP1が正常に機能しないこと、そのためにスプライシング異常が生じて様々な遺伝子の発現に乱れが生じることが原因と考えられます。さらに、このようなメカニズムは他の知的障害にも起こりうることと想定されます。これらの結果はNature Communicationsに報告されました。(詳しい内容を見る
 )
)
- 2014年4月30日
- <プレスリリース>慶應義塾大学医学部生理学教室(岡野栄之教授、岡田洋平訪問准教授)・小児科学教室(沼澤佑子助教)らの研究グループは、先天性大脳白質形成不全症のひとつであるペリツェウス・メルツバッハー病(Pelizaues-Merzbacher disease:PMD)の二名の患者さんから人工多能性幹細胞(iPS細胞)を作製し、髄鞘形成に重要なオリゴデンドロサイトへと分化誘導することで、小胞体ストレスに対する脆弱性や髄鞘形成不全などの病態を試験管内で再現することに成功しました。また二例のPMD患者由来オリゴデンドロサイトで観察された変化の多くは患者の重症度をよく反映しており、髄鞘形成不全症の疾患モデルとして有用であると期待されます。本研究成果は「Stem Cell Reports」のオンライン版に掲載されました。(詳しい内容を見る)
- 2014年4月16日
- <プレスリリース>林 康紀シニアティームリーダー(理化学研究所脳科学総合研究センター、兼、埼玉大学脳末梢科学研究センター)らはマサチューセッツ工科大学脳認知学部ピカワ学習と記憶研究所と共同研究で、学習・記憶の分子メカニズムの鍵となる現象を見いだしました。米国学術誌“Neuron” (Boschら2014年4月16日発行)に発表された論文で、著者らは樹状突起スパインの内部構造が、時空間的にどのように変化する事でシナプスの伝達が強化されるかを明らかにしました。彼らは、シナプスの様々な構成要素が整然と順番に増加していく様子を明らかにしました。一番始めに増加するのはアクチンおよびアクチン結合タンパク質でした。この増加によってシナプスの形態が大きくなりました。そして1時間程度経つと、次に足場タンパク質と呼ばれるタンパク質がシナプスへ流入し、一旦拡大したシナプスをその状態に安定化させました。このようにシナプスにて様々な因子が特定の順序で増加してくる事には、何らかの因果関係がある事が示唆されます。さらに中でもアクチン結合タンパク質であるコフィリンの増加が他のタンパク質と比較して著しい事、それが拡大したシナプス構造の維持に重要である事を示しました。
- 2014年4月2日
- <プレスリリース>公募班員・星野幹雄(国立精神神経医療研究センター神経研究所・部長)らのグループは、神経幹細胞の「位置情報」を制御することによって多様な神経細胞を生み分ける新たな仕組みを明らかにしました。星野らは2014年2月に小脳の神経幹細胞の「時間情報」を制御するしくみについて報告していましたが(Nature Communications, 5, 3337, 2014)、本研究ではさらに、Ptf1aとAtoh1という二種類の転写因子(タンパク質)が小脳の神経幹細胞に「位置情報」を与えることによって、それぞれの神経幹細胞が抑制性および興奮性グループの神経細胞を生み出すようになるというメカニズムを、遺伝子改変マウスを用いて明らかにしました。本研究成果は、Journal of Neuroscience誌に掲載されました。(詳しい内容を見る
 )
)