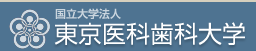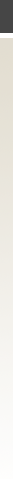 |

|
| |
| |
「アトピー性皮膚炎などの慢性アレルギーをひきおこす
新たなメカニズムが明らかにされた」
東京医科歯科大学の烏山教授のグループが中心となって進めてきた共同研究成果について、8月22日(月)、本学特別講堂において記者会見を行い、「血液中を流れる白血球の0.5%を占めるに過ぎない少数集団である好塩基球と呼ばれる細胞が、実は、慢性アレルギーの発症に深く関わっていることが判明した」と発表しました。

|
(中央)烏山 一 教授 (本学大学院医歯学総合研究科免疫アレルギー学分野)
(右)横関 博雄 教授 (本学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野)
(左)米川 博通 副所長 ((財)東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研究所)
|
 | ポイント |
- 血液中を流れる白血球の0.5%を占めるに過ぎない少数集団である好塩基球と呼ばれる細胞が、実は、慢性アレルギーの発症に深く関わっていることが判明
- 白血球のひとつであるT細胞が慢性アレルギーの発症に重要であることがわかっていたが、それとはまったく別の慢性アレルギー発症のメカニズムがあることが判明
- 好塩基球を標的にした新たな慢性アレルギー治療法開発の可能性
 | 研究成果の概要 |
日本を含めいわゆる先進諸国では、花粉症をはじめとするアレルギー性疾患が年々増加傾向にあり、国民の3割近くが何らかのアレルギー症状を示すといわれるまでになっています。とくにアトピー性皮膚炎や喘息などの慢性アレルギー疾患は重篤で、現在までのところ有効な根本治療法が見いだされていないため、患者の肉体的、精神的、経済的負担は大きく、深刻な社会問題となっています。この慢性アレルギー疾患の発症メカニズムの解明と新規治療法の開発をめざして、東京医科歯科大学では大学院医歯学総合研究科・免疫アレルギー学分野の烏山一教授のグループが中心となって、同皮膚科学分野、包括病理学分野ならびに東京都臨床医学総合研究所の研究グループと共同で研究を進めてきました。
今回の研究では、アレルギー患者と同様に血液中のIgE(アレルギーをひきおこす物質「アレルゲン」に反応する抗体の1種)量が多いモデル動物を作製して、アレルゲンを投与した場合に生じる皮膚アレルギー症状を詳しく解析しました。その結果、アレルギー反応をひきおこす主役として知られているマスト細胞やT細胞がまったく存在しない状況でも、長期に続く慢性アレルギー炎症がおき、その発症には好塩基球が必須であるという新事実が明らかとなりました。好塩基球は血液中を流れる白血球の0.5%を占めるに過ぎないマイナーな細胞集団で、これまでほとんど注目を集めることがありませんでしたが、今回の研究によって、従来考えられていたものとはまったく別のメカニズムにより、好塩基球が慢性アレルギーをひきおこすことが判明しました。
この画期的研究成果は、米国の免疫学専門誌Immunity(Cell Press社)8月号に発表されます。この発見により、アトピー性皮膚炎や喘息に代表される慢性アレルギー疾患の複雑な発症・悪化の仕組みが解き明かされ、新規治療法の開発にはずみがつくものと期待されます。
※プレスリリースの詳細は こちら
 | 問い合わせ先 |
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
免疫アレルギー学分野
烏山 一 (からすやま はじめ)
TEL 03-5803-5162 FAX 03-3814-7172
e-mail: karasuyama.mbch@tmd.ac.jp
研究室ホームページ http://www.tmd.ac.jp/med/mbch/Immunology
|
|
|
 |