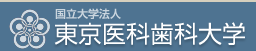|
東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・免疫アレルギー学の烏山一(からすやま はじめ)教授の研究グループは、同・生命倫理研究センターならびに東京大学・大学院医学系研究科・細胞情報学の研究グループとの共同研究で、これまで知られていなかったアナフィラキシー・ショック(ペニシリン・ショックが有名)の新たな発症機構を発見しました。この研究は、文部科学省研究費補助金の支援でおこなわれたもので、その研究成果は、米国科学誌Immunityの2008年3月13日付オンライン版で発表されました。
|
|

烏山 一 教授
本学大学院医歯学総合研究科
免疫アレルギー学分野
|