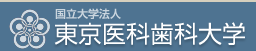|
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学の高柳広教授らのグループは、東京大学医学部神経生化学の尾藤晴彦助教授らのグループと共同し、骨量を減らす破骨細胞の形成や機能に必要な物質として酵素カルモジュリンキナーゼIVと転写因子CREBを同定し、その阻害剤が骨粗鬆症や関節リウマチの骨破壊の治療に有効であることを動物実験で示しました。本研究は、東京医科歯科大学大学院21世紀COEプログラム「歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティア」(COE拠点リーダー・野田政樹教授)の一環として行われたものです。この研究成果は米国の医学雑誌Nature Medicine の12月号に掲載されました。
|
|

高柳 広 教授
大学大学院医歯学総合研究科
分子情報伝達学分野
|