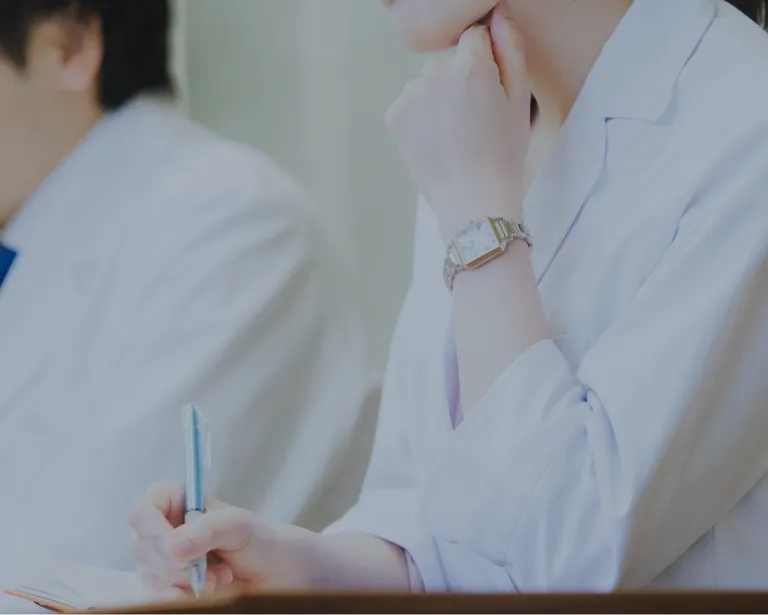

VOICE
受講生・修了生の声
2025年度受講生
山口 峻平さん
在宅緩和ケアの質向上を目指して~病院チーム研修での学びを地域に~
在宅医療で緩和ケアに携わる薬剤師として、日々患者さんやご家族と向き合っています。しかし病院のように専門医や緩和ケアチームが常にそばにいるわけではなく、在宅医療では患者ごとに関わるクリニックや訪問看護が異なるため、チーム体制の構築に課題を感じていました。より専門的な視点を学び、在宅での実践に活かしたいと考え、今回の研修に参加しました。
慶應義塾大学病院の緩和ケアチームでの5日間の研修では、朝のカンファレンスから病棟ラウンド、外来対応、終診カンファレンスまで現場に密着しました。緩和ケア専門医3名に加え、専属の緩和ケア薬剤師や看護師が在籍し、互いの専門性を尊重しながら多角的に意見を交わし、最適な方針を練り上げていく様子を間近で見ることができました。
特に印象的だったのは、緩和ケアチームが一体となって患者さんの状態を診て、疼痛評価や副作用確認を行い、医師が判断に迷う場面では専属薬剤師が薬剤特性や症状変化を見越した適切な回答を迅速に行い、それを主治医にもすぐに共有する姿勢でした。私の疑問にも一つ一つ丁寧に答えていただき、患者さん・主治医双方に寄り添うチームの在り方が深く心に残りました。
この研修で得た知識と姿勢は、在宅緩和ケアにも十分応用できると感じています。チームが固定されない在宅医療だからこそ、薬剤師が疼痛評価や薬剤選択提案にとどまらず、訪問看護や在宅クリニックとの緩和ケアに関する知識の共有、カンファレンスを通じた振り返りや次のケアへの改善に積極的に関わることが重要な役割だと実感しました。誰一人取り残すことなく、患者さんとご家族が安心して自宅で過ごせる緩和ケアを地域全体で支えていきたいと思います。
2024年度受講生
私は現在、慶應義塾大学大学院医学研究科でがんプロフェッショナル養成プログラムに所属し、がん患者さんに対する医療の提供と研究を進めております。私が「がんプロフェッショナル養成プログラム」を志望した理由は、がん患者さんに対する全人的な医療を提供できるような医療者になること、それを達成するチームを作る人材になりたかったからです。私は医師となり現在6年目となりますが、市中病院で研修していた際に多くのがん患者さんの臨床を経験し、外科的切除によって根治できる方や残念ながら病期が進行して亡くなる方もいました。その経験の中で、がんという疾患への学問的探究心と自分の専門分野だけでない知識と考え方の習得によって、より良い医療や知見を患者さんに提供できるようになりたいと思いました。
本コースの最大の特徴は基礎腫瘍学や緩和医療学といった、さまざまな分野の第一線で活躍されている先生の講義を聴講できるだけでなく、研究手法として重要な統計の講義・実習も充実し、研究のプロセスや実施方法に関しても学べる点です。また、現在は講義のみの参加となっていますが、今後は必須診療科(血液内科・緩和ケア・放射線治療)の実習も始まる予定であり、非常に楽しみにしています。加えて、現時点では未定ですが、がん診療のハイボリュームセンターである連携施設での研修も希望しており、慶應以外でも多くの経験を吸収しようと思っています。
本コース修了後は、次世代のがん医療を支える人材になれるよう努めていきます。
2024年度受講生
井上 玲香さん
私は緩和薬物療法認定薬剤師として、緩和ケア病棟と緩和ケアチームで薬剤提案を行っている。しかし知識や経験不足を感じ、どうすれば薬剤師として患者さんが抱えている「苦痛」や「不安」に寄り添うことができるのか学ぶため受講した。
慶應義塾大学病院の緩和ケアセンターでは、身体症状担当医師、精神症状担当医師、看護師、薬剤師が毎日回診、カンファレンスを行っている。研修では緩和ケアチームに同行し、多職種でディスカッションする機会をいただいた。
画像診断やフィジカルアセスメントによる疼痛評価を行い、添付文書やインタビューフォーム、最新の論文を読み解いて、薬物動態や薬理機序に基づいた、薬剤選択や投与量、投与方法の提案が行われていた。また、患者さんの思いや価値観を重視したケアや治療を行うためのコミュニケーション法を学んだ。
痛み診療センターでの研修は、非がん性慢性疼痛について受講し診察に同席させていただいた。薬物療法や神経ブロックを見学し、当院では行っていない治療法を学び治療の選択肢を考えるきっかけとなった。
私が目指す緩和医療専門薬剤師は、身体マネジメントの実践能力、患者とのコミュニケーション能力、緩和医療の質の向上に貢献できる研究力を有することが課せられている。今回の研修で、日々の業務を振り返り今後学ぶべきことが明確となった。
「患者の苦痛を理解し、寄り添う痛みの治療・ケア、終末期医療を担う専門家として、誰一人取り残さない治療を提供する」ことが、がんプロフェッショナル養成講座の主旨である。今後は研修で学んだことを活かし、多職種と連携しながら地域において緩和ケアを推進していきたい。
2024年度受講生
中嶋 康記さん
私は現在、国立がん研究センター東病院リハビリテーション科で、がん患者に対するリハビリテーション医療を提供しています。この度、ライフステージ別がんリハビリテーション習得コースを志望した理由は、がん患者の病期やライフステージに合わせたリハビリテーションを学びたいと考えたからです。また、がん医療の現場で直面している課題の解決や、新しい治療法の開発に貢献できる人材になることを目指しています。
本コースで感じた最大の魅力は、各分野の第一線で活躍されている先生方から、がんのリハビリテーション診療において最新の知見や臨床研究について直接学べたことです。周術期から緩和ケアの時期に応じた知識やスキル、病期に合わせた実践方法についての講義を受け、学んだことは日々の臨床に大変役立っています。臨床研究に関する講義では、研究のプロセスや実施方法について学びました。また、症例検討会やグループワークを通じて自身の研究計画を発表し、統計手法や交絡因子、バイアスなどについて具体的な指導を受けることで、体系的に知識を身につけることができました。さらに、辻教授や他施設の専門職の方々と意見交換を重ねる中で、研究の目的をより明確にすることができた点も魅力の一つでした。本コースを通じて、自分自身の研究をさらに深めるための目的がより明確となり、がんのリハビリテーション分野における新規支持療法の開発に貢献したいと強く思いました。
本コース修了後は、がんのリハビリテーション分野でさらに専門性を高め、次世代のがん医療を支える人材になれるよう努めていきます。
2024年度修了生
鷹箸 由貴さん
私は数年間、病棟で看護師として勤務してきましたが、より専門的ながん看護を学びたいと思い、がん看護専門看護師(がん看護CNS)を志し、修士課程のがん看護CNSプログラムに在籍しました。このコースでは、がん医療に関する医学研究科の講義の受講、病院実習、がん看護学の教育国際セミナーに参加する機会があります。
講義では、臨床腫瘍学や緩和医療など各専門領域において、がんの病態や治療方法、今まで行われてきた研究について学び、最新の知見や先生方の考えを知ることができました。病院実習では、がん薬物療法や緩和医療の専門医、病棟や外来で働くがん看護CNSの方々の活動を見学したり、アドバイスを頂きながら、CNSとしての役割や、役割発揮に必要な能力を学びました。2024年度のがん看護学教育国際セミナーでは、修士論文の研究方法として学んでいた質的研究の再帰的テーマ分析について、著者のVirginia Braun先生から直接講義を受け、再帰的テーマ分析の概念や分析プロセスを学ぶことができました。
がん医療に携わる各分野のプロフェッショナルの方々が持つ幅広い知識や専門分野への熱意、そして緻密な思考に基づく行動に触れ、私は強く感銘を受けました。1つ1つの学びが、これまで自分が狭い視点で物事を捉えていたことに気付かせてくれる貴重な機会となり、自分の視野を大きく広げることができました。本プログラムで得た学びを活かし、今後は看護師として、がん患者さんとそのご家族によりよい支援ができるような看護を探求し、実践につなげていきたいと考えています。
2024年度修了生
中嶋 康記さん
本コースでは、がんリハビリテーション領域の第一線で活躍される専門家から、治療前リハビリテーション、周術期から緩和ケア主体の時期に至るまでの各病期の治療アプローチ、そして最新の臨床知見まで、包括的な指導を直接受けました。特に、ライフステージ別の運動腫瘍学(Exercise Oncology)に関する体系的な講義は、新たな視点を与えてくれました。臨床研究のセッションでは、研究計画の立案から統計解析、交絡因子やバイアス制御まで、研究遂行に不可欠なスキルを体系的かつ実践的に習得しました。さらに、辻教授や他施設の専門職との症例検討・グループディスカッションは、自身の研究課題を多角的に見つめ直し、精緻化する貴重な機会となりました。これらの経験を通じ、がんリハビリテーション分野における新たな支持療法を開発し、エビデンスを創出することへの意欲がより一層確固たるものになりました。
コースで得た知見と研究への熱意を原動力に、修了後は本学大学院修士課程に進学しました。大学院では、個別化医療や先端ゲノム医学といった最新の動向から、基礎研究および臨床試験を通じた新薬・新規医療技術の開発、臨床研究の立案・計画・実践、医学倫理・関連法規を体系的に学び、医学統計学や腫瘍学の専門知識を深めることで、臨床と研究を繋ぐ実践的スキルを一層高めることができました。
これらの学びを臨床現場に還元し、がんチーム医療におけるリハビリテーション専門職として実践能力向上に努めています。今後は、臨床研究を計画・遂行する学術的知識と実践的技能をさらに磨き、国内外の臨床・研究活動を通じて、がんリハビリテーション分野を牽引する指導的人材となるべく、研鑽を重ねていく所存です。

 受講生・修了生の声一覧へ戻る
受講生・修了生の声一覧へ戻る