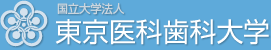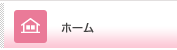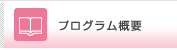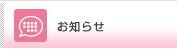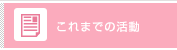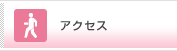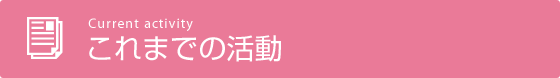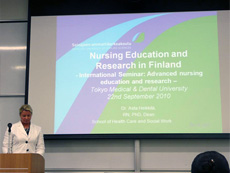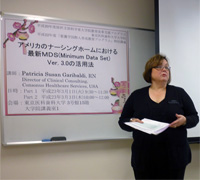������20�N�x��
������22�N�x��
�Ō�w���ېl�琬����v���O�����ɂ�鎋���o���ޏ��
���Đ��{�^���������Ɗe�c�u�c�̃T���v�����悪�����ɂȂ�܂��B�i�vFlash player8�ȏ�j
�P�D�u�Ō�w���ېl�琬�𐄐i�����w�@����v
|
|
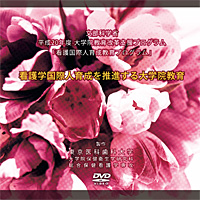 |
|
| �Q�D�uEnglish Communication Skills for Graduate Students of Nursing�v�iAll English�j | |
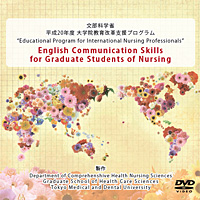 |
|
| �R�D�uEnglish Presentation Skills for Graduate Students of Nursing
�@�@ �\�Ō�n���ۊw��ɂ�����v���[���e�[�V�����Z�@�\�v |
|
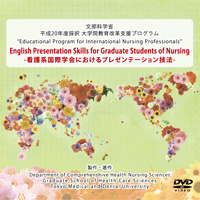 |
|
| �S�D�uGraduate School Education for Promoting �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ International Nursing Professionals (all English)�v �@�@ |
|
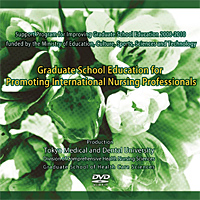 |
|
| �T�D�u�A�J�f�~�b�N�E�p�u���P�[�V�����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���ۊw�p���ւ̊Ō쌤���_�����e�@�\ (CD-ROM)�v |
|
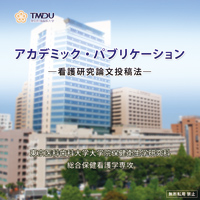 |
|
|
�@�@�@��]�҂ɂ͎����o���ނ�z�z���Ă���܂��B �@�@�@����]�̕��́A e-mail�ɂĉ��L�܂ł��₢���킹���������B �@�@�@���₢���킹�F�@������Ȏ��ȑ�w��w�@�@�Ō�w���ېl�琬����v���O���������ǁi�c���j �@�@�@E-mail address �Ftanuma.phn@tmd.ac.jp |
INTERNATIONAL SEMINAR
| �gAdvanced Nursing Education and Research�h ���ۃZ�~�i�[�@�u�Ő�[�̊Ō싳��ƊŌ쌤���v  �I�[�v�j���O�F��R�w�����A �� ���F����22�N9��22��(��) 10:30�`17:00 �u �t�FProf. Anne Peat (Dean, School of Nursing & Midwifery, University of Sheffield, UK), �@�@�@�@Dr. Kathy Magilvy (Associate Dean, University of ColoradoDenver, USA ), �@�@�@�@Dr. Fu-jin Shih (Dean, National Yang-Ming University, TAIWAN), �@�@�@�@Dr. Asta Heikkilä(Dean, School of Hearth Care and Social Work, �@�@�@�@�@�@ SeinäjokiUniversity of Applied Sciences, FINLAND) �� ��FM&D�^���[�i�㎕�w�����������U�����j2�K�@���p�u�`��2 |
|
��Quality Assurance and Enhancement in Higher Education��
Prof. Anne Peat (Dean, School of Nursing & Midwifery, University of Sheffield, UK) ���̍u�`��ʂ��āA����ɖ��������A���s�E�]���E���P�̃X�e�b�v���J��Ԃ��Ă������ƂŁA�P�A�̎��̌���ɓw�߂邱�Ƃ��d�v�ł���Ƌ����������B�C�M���X�ł͌��s�̋�����e�̃t�B�[�h�o�b�N�⍂��������u���l�̑I���̗ƂƂ��邽�߂ɁA���ƕ]���̌��ʂ����J���Ă���A���Ǝ��̂����Ԃ���]������Ă���Ƃ������Ƃ����Ɉ�ۓI�������B |
||
|
��Nursing Education and Research in USA, Taiwan, and Finland>
Dr. Kathy Magilvy (Associate Dean, University of ColoradoDenver, USA) |
||
|
Dr. Fu-jin Shih (Dean, National Yang-Ming University, TAIWAN) �o�ϔ��W�̒�������p��Yang-Ming��w�̋���V�X�e���ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł����B�Ō�̎������߁A���ۓI��������Ō�̐��Ƃ̈琬�̕K�v���́A���{�Ƃ����ʂ��Ă��邱�Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł����B |
||
|
Dr. Asta Heikkilä(Dean, School of Hearth Care and Social Work, SeinäjokiUniversity of Applied Sciences, FINLAND)
�@ �t�B�������h�ł̊Ō싳��ɂ��Ċw�B�t�B�������h�ł͓��{�Ɠ��l�ɁA�p�u���b�N�w���X�i�[�X�ƊŌ�t�̋�����s���Ă������߁A�e�ߊ������Ă��B����ŁA���Ǝ����͂Ȃ��A�e��w���C���Ɠ����ɊŌ�t���i���擾�\�ł���A�e��w�Ŏ��̑������Ō싳�炪�s���Ă��邱�Ƃ��z���ł����B�܂����p���92%���t�B�������h�ꂾ���A��w�̎��Ƃ��p��ōs���ȂǁA�Ō삪���ۓI�ɋ�������K�v������������A�Ō�ɂ����鍑�ۋ��͂̕K�v�������߂Ċ����邱�Ƃ��ł����B |
||
|
����22�N�x�@�Ō�w���ېl�琬����v���O�����ɂ��C�O�h����
| ����23�N(2011�N)���k�n�������m���n�k�ɂ���X�̉e������A �W�ł̎��ʔ��\�ɕύX�������܂����B ��]�҂ɂ͕W��z�z���Ă���܂��B �@����]�̕��́A e-mail�ɂĉ��L�܂ł��₢���킹���������B ���₢���킹�F�@������Ȏ��ȑ�w��w�@�@�Ō�w���ېl�琬����v���O���������ǁi�c���j E-mail address �Ftanuma.phn@tmd.ac.jp |
���ʍu�`
| �A�����J�̃i�[�V���O�z�[���ɂ�����ŐV�l�c�r(Minimum Data Set)Ver. 3.0�̊��p�@ �����F�P�D����23�N3��1��(��) 9��30���`11��30�� �@�@�@ �Q�D����23�N3��3��(��) 10���`12�� �u�t�FMs. Patricia Susan Garibaldi, RN (Director of Clinical Consulting, Consonus Healthcare Services, USA) ���F3����15�K�@��w�@�u�`��1 |
����҃A�Z�X�����g�c�[���Ƃ���MDS2.0���g�p����Ă��邪�A���݃A�����J�Ŏg�p����Ă��������MDS3.0�̊��p���@����b�g�ɂ��Ċw�B�e���ڂ̓��e�A�����]���̕��@�̑��ADVD�����p���A�I���S���B�̃i�[�V���O�z�[���ł̍���҂��畷����邽�߂̋�̓I�ȕ������̎�@�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł����BMDS3.0�̓����́AMDS2.0���������̃A�Z�X�����g���ڂƃC���^�r���[���ڂ��݂����Ă���_�ɂ���B���ɔF�m�ǁA���_�����A�ɂ݂Ɋւ���C���^�r���[���ڂ�݂������Ƃɂ��A����҂̃A�Z�X�����g�����[���s�����Ƃ��ł��A��ÎҁE����҂ɂƂ��āA���悢�P�A�ɂȂ���Ɗ������B |
|
 |
���ʍu�`
| �t�B�������h�̃w���X�P�A�ɂ����鋳��ƌ��� �`����҃P�A�ƍݑ�P�A�̒���` �����F����23�N3��3��(��) 14���`16�� �u�t�FMs. Helli Kitinoja, RN MNSc (Manager of International Affairs Seinäjoki University of Applied Sciences, FINLAND) ���F3����15�K�@��w�@�u�`��1 |
�t�B�������h�ɂ����鍂��҃P�A�ƍݑ�P�A�̎���ƁA����Ɋւ��Ō�t�̐�勳�炩��n�C���x���ȋ���ɂ��Ċw�B�܂��A�Z�C�i���L���p�Ȋw��w�Ɩ{�w�Ƃ̋����ł̋���⌤�������̓W�J�ƓW�]�ɂ��Ă̒�N���Ȃ��ꂽ�B����A�܂��܂�����w�Ԃ̌���������w���̋���E�𗬂����������Ă������Ƃ����҂��ꂽ�B
|
|
 |
�p��ɂ��Ō쌤���v�揑����ј_���̍Z�{
| �u�t�FMs Patricia Susan Garibaldi, RN �����F ����23�N3��2��(��) 14:00-16:00 �ꏊ�F ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�����ی��Ō�w��U������ |
|
�č��Ɠ��{�̊Ō�ɂ����鐧�x�̔�r���s���A�K�ȊŌ�p��̊��p���@�⌤���v��̗��ĕ��@�ɂ��ċ��������B�܂��ʂɁA�w�������ݎ��g��ł���p��_���̍\���⌤���v�揑�̓��e�Ȃǂɂ��āA��̓I�ȃA�h�o�C�X���B
|
�p��R�~���j�P�[�V�����u��
| �u�t�FMs Patricia Susan Garibaldi, RN �@�@�@ Ms Helli Kitinoja, RN �����F�i1�j����23�N2��28��(��)14:00�`16:00(Ms Kitinoja�̂�) �@�@�@ �i2�j����23�N3��1��(��)13:30�`16:00�@ �@�@�@ �i3�j����23�N3��2��(��)10:00�`12:00 �@�@�@ �i4�j����23�N3��4��(��)14:00�`16:00(Ms Garibaldi�̂�) �ꏊ�F������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�����ی��Ō�w��U ������ |
|
�Ō�p��R�~���j�P�[�V�����u���ł̃e�[�}�́A�����Ⴄ���e�Ői�߂�ꂽ�B�Q�������w���̉ۑ�A���݊w�����s���Ă��錤���e�[�}�A�č���t�B�������h�̊Ō슈���̌���Ɠ��{�̉ۑ�ȂǁA����̃Z�b�V�����̓��e�͑���ɂ킽�����B���ꂼ��̊w�������g�̊Ō쌤���Ɋւ���l����v�����A�p��ɂ��\���ɓ��_���邱�Ƃ��ł����B
|
���ʍu�`
| Home Care & Preventive Visits in Denmark�@�f���}�[�N�ɂ�����ݑ�P�A�Ɨ\�h�K�� �����F����23�N1��17��(��)10���`12�� �u�t�FMs. Lene Holländer (Home Care Consult, Care Academy of Denmark) ���F3����15�K�@��w�@�u�`��2 |
�Љ�����ƂƂ��Ė������f���}�[�N�ɂ����钷���珰����҃P�A�A�Q������\�h�A24���ԍݑ�P�A�A�\�h�K��ɂ��āA�搶�̌o���������Ă��b�������B���҂���X�l�̎����⎩�R�d�����s���͂����P�A���A�l�X�ȃv���t�F�b�V���i���ɂ���Ď��{����Ă���A���{���w�Ԃׂ����͑�R����Ǝ��������B
|
���ʍu�`
| Research Trend in the USA �Q �u�t�F Dr. Patricia Grady�iDirector of National Institute of Nursing Research, USA�j ���ʍu�`�F ����23�N1��8��(�y)10���`12���@(M&D�^���[���p�u�`���Q) �e�[�}�FNational Institute of Health and National Institute of Nursing Research: Supporting Excellence in Science |
NIH��NINR�̃~�b�V�����A���j�A�g�D�A�\�Z�ɂ��Ă̍u�`�ł������BNIH��27�̉����g�D��1�Ƃ���NINR������A�Ɨ����ė\�Z�Ă���B�A�����J�o�ς��s���̒��A�\�Z�͑��z����Ă���A���ʂ��s���ɊҌ����Ă������Ƃɗ͂����Ă���B�܂����̌����@�ւ����g���[�j���O�ɗ͂����Ă��邱�ƂȂǁANINR�̌����l�����ȂNJw�Ԃ��Ƃ��ł����B |
����23�N1��12��(��)�E13��(��)
12�E13���̍u�`�ł͊w���������̌����v����p��Ńv���[���e�[�V�������s���ADr.Grady��蒼�ڍu�]��A�h�o�C�X�����炢�p��Ńf�B�X�J�b�V�������s��ꂽ�BNINR�̑��l�҂ł���搶�̑O�Ńv���[�����s�����߂̏�������ۂ̃v���[�����s�����ƂŁA���ۓI�ȃA�J�f�~�b�N�v���[���e�[�V�����̕��@���w�Ԃ��Ƃ��ł����B |
����23�N1��12��(��)13���`16��10���@(M&D�^���[���p�u�`���Q) �e�[�}�FNINR: Bringing science to life NINR�Ŏ��g��ł��錤���̃g�s�b�N�Ɠ��e�A���ʂɂ��Ă̗Ⴊ�Љ��A�������s���ۂ̐S�\���⑼����Ƃ̋��������ɂ��Ă������Ē������B �e�[�}�FFunding and training opportunities �l�X�Ȍ��������@�ւ̃t�@���h�⌤���@�ւł̃g���[�j���O�E�t�F���[�V�b�v�ւ̉���ɂ��Ă��w�B |
����23�N1��13��(��)8��50���`12���@(M&D�^���[���p�u�`���Q) �e�[�}�FGrantsmanship Overview NINR�̌�������ւ̉�����@��ǂ̂悤�ɍ̑��E��̑������肳��Ă���̂��ǂ̂悤�Ȏ��_�ŕ]�����s���Ă���̂��Ƃ������Ƃ���̓I�Ɋw�ׁA������ۂɎ������������傷�鎞�ɖ𗧂ł��낤��R�̏���ꂽ�B �e�[�}�FFunding and training opportunities �Ō�̎��ۂƂ��ꂩ��ɂ��Ċw�B���ۂ̊Ō쌤���҂̌��������ƂŎЉ�ɕω��������炵����������A�����������Ō쌤���҂Ƃ��Ăǂ̂悤�ɃA�v���[�`���Ă����ׂ��Ȃ̂����l����������u�`�ł������B |
���ʍu�`
| Research Trend in the USA �P �u�t�FDr. Mary Sue Heilemann (Associate Professor, University of California, Los Angels) ���ʍu�`�F ����22�N12��17��(��) 2���FCognitive Therapy Techniques for Depression (3����15�K�@��w�@�u�`��2) �F�m�s���Ö@�Ƃ͉����A�ǂ̂悤�ȉ�����s�����̂Ȃ̂����A�搶�̌����E���H���瓾���o���������Ă��b�����������B�A�����J�ł͊Ō�̏�ʂɂ����Ă��F�m�s���Ö@�̊��p���ϋɓI�ɂȂ���Ă���A�Ō�t�����Z�p���w��ł��܂��܂ȃA�v���[�`���s���Ă��邱�Ƃ��w�B ����22�N12��20��(��) 2���FSituational Analysis (3����15�K�@��w�@�u�`��2) ���I�����̎�@�Ƃ��ď���situational analysis�ɂ��Ċw�B��@�̓N�w�I�Ȕw�i��A���j�I�A�����I�ȕω��ɂ��e����m�邱�ƂŊT�O�ւ̗������i�B�܂����ۂɊw���̌����e�[�}�̈ꕔ�����Ƃ̒��ŕ��͂��Ȃ���A�K�v�ȏ��̕\�����A���͂̑�܂��ȗ���ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł����B ����22�N12��22��(��)13:00�`16:10 �FAcademic Career Development of the Nurse Scholar(3����18�K�@�u�`��1) �����̉��l�ς̔��B���͂��߁A�Ō�t�Ƃ��Ẳ��l�ρA�Ō쌤���ւ̃��`�x�[�V���������߂邱�Ƃ̏d�v���A�Ō�Ȋw�҂Ƃ��ĐV�������o�����V�����Ō�̒m���������̒��łǂ��������Ă����̂��ɂ��Ċw�B |
���ʍu�`
| Ethnographic Research in Nursing �|�Ō�w����ɂ�����G�X�m�O���t�B�[�̌������@�| �� ���F���� 22�N9��24���i���j9:30�`10:30 �u �t�FDr. Kathy Magilvy, PhD, RN, FAAN (University of Colorado Denver, USA) �� ��F3���فi���T�����j15�K�@��w�@�u�`��2 |
�Ō�̎��I�����ɂ����ďd�v�ȕ��@�̈�ł���G�X�m�O���t�B�[��p�����������@�ɂ��Ă̍u�`�����B�T�ςƌ����̃f�U�C������@���w�сA��̗��ʂ������p���@�ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ��ł����B
|
���ʍu�`
| Tips for Success as a Global Nurse Researcher
�� ���F����22�N9��24���i���j10:30�`15:30 �u �t�F��g�e�I�@�h�q(University of California, San Francisco, USA) �� ��F3���فi���T�����j15�K�@��w�@�u�`��2 |
�Ō�̎��I�����ɂ����ďd�v�ȕ��@�̈�ł���G�X�m�O���t�B�[��p�����������@�ɂ��Ă̍u�`�����B�T�ςƌ����̃f�U�C������@���w�сA��̗��ʂ������p���@�ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ��ł����B
|
���ʍu�`
| �k���ɂ�����Hospital Play Therapist�̐��x�Ɗ���
�� ���F2010�N8��16��(��)�@16�F00�`17�F00 �u �t�FMrs. Tove Smedsrod �i Hospital Play Specialist, �g�����\��w�����a�@ , Norway �j �� ���F������Ȏ��ȑ�w3����15F �@��w�@���Q |
�m���E�F�[�ɂ����鏗���̌ٗp��q��Ă̌���A�v���C�E�Z���s�X�g�̖����Ƌ�̓I�Ȋ����ɂ��Ċw�B�q�ǂ����V�т�ʂ��Ď��ÂɑO�����ɂȂ�ߒ����A�L�x�Ȏ���������Đ������ꂽ�B�Ƃ�킯�A�g�����\��w�t���a�@�ł͗V�т�ʂ��Ďq�������̐��� (play&listen) ���Ƃ��d�v�����Ă����B���^�����ł́A�u�t�̋Ζ�����a�@�ł̊��Ґ���Z���s�X�g�̐��A�����Ƃ̈Ⴂ�Ɋւ��鎿�₪����A�����ȓ��c���s��ꂽ�B
|
���ʍu�`
| �����z����w�ɂ�����Ō싳��ƌ��� Nursing Education and Research in NYMU
�� ���F2010�N7��15��(��)�@16�F00�`17�F00 �u �t�FDr. Yiing Mei Liou�i�����z����w, ��p�j �� ���F������Ȏ��ȑ�w3����15F �@��w�@���Q |
��p�ɂ�����Ō싳�炨��ъŌ쌤���̌���ɂ��āA�w�Ԃ��Ƃ��ł����B |
���ʍu�`
| Academic Writing and Publication
�� ���F2010�N6��24��(��) 14:30�`16:00 �u �t�FProf. Roger Watson, BSc, PhD, RN, FFNMRCSI, FHEA, FRSA, CBiol, FSB, FRCN, FAAN �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�V�F�t�B�[���h��w�Ō쏕�Y�w���@�����A�p���j �� ���FM&D�^���[�Q�K�@���p�u�`���Q |
�{�w�̒�g��w�̈�ł���V�F�t�B�[���h��w���炨���ł����ł���������Prof. Roger Watson����A�Ō�p��_�����e�̎�@�ɂ��Ċw�B���{�ɂ�����Ō쌤���̐��ʂ̔��M�́A�܂��܂��L�x�Ƃ͂����Ȃ��ɂ��邱�Ƃ��Ɋ����ꂽ�B��̓I�Ȏ���ɂӂ�Ȃ���A�w�p�_���̏������A�z�����ׂ��|�C���g�Ȃǂ��w�Ԃ��Ƃ��ł��A�ϋɓI�ɐ��E�ɔ��M���Ă����w�͂𑱂��Ă������߂̃��`�x�[�V����������ꂽ�B
|
���C�w���̎���
| ���@�ԁF2010�N�V��11���`25��(2�T��) |
�����z����w(��p)����A�w���w��4�������ꂽ�B
���{�y�і{�w������Ō싳��ɂ��Ă̍u�K���s�����B�܂��A�{�w�t���a�@��Ō�A�[�c���[���ł̌��C���s�����B�O���@�ւƂ��āA�Љ���@�l������A���H�����ەa�@�A�Ɨ��s���@�l���������Ì����Z���^�[�a�@�A�Вc�@�l���{�Ō싦��A�����ی����������g�����V�l�ی��{�݂Ђ��킵���A���ŃC���t�H���[�V�����V�X�e���Y������Ђ⑫����|�̒˕ی������Z���^�[�E�]�k�ی������Z���^�[�̂����͂邱�Ƃ��ł��A���L������ɂ킽�錤�C���e���[�������邱�Ƃ��ł����B
4���̊w���͓��{�̊Ō�ɂ��đ��p�I�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł��A��p�Ɠ��{�̊Ō�A���ꂼ��̒��������������߂̎�����ꂽ�B
|
������21�N�x��
����22�N3���@���J�u��
| �t�B�������h�ɂ�����ی������{��ƊŌ싳��|���̐헪�| �`Strategy of health care and welfare policy and nursing education in Finland�` �� ���F2010�N3��27���i�y�j 10�F00 �` 16�F00 �� ���F�����K�[�f���p���X�z�e���@���P�̊� |
||||||||||||
| ||||||||||||
|
|
(�ߌ�)
|
�Ō�w���ېl�琬����v���O�����ɂ��C�O�h����
| �� ���F2010�N3��23��(��) 13��30���`
�� ���F�T���� 15�K��w�@�u�`���Q |
||
| ||
���� 21�N�x�@�Ō�w���ېl�琬����v���O�����ɂ��C�O�h��
�h���� ( �h���� ) |
�h������ |
�h���l�� |
|
�P�j |
Seinäjoki University of Applied Sciences
( FINLAND ) |
�@2009�N 8�� 31���` 9�� 18�� | 4 �� |
�Q�j |
Oregon Health Science University (USA) | �@2010�N 1�� 25���` 2�� 12�� | 1 �� |
�R�j |
Akron University, College of Nursing (USA) | �@2010�N 1�� 31���` 2�� 5�� | 1 �� |
�S�j |
University of Sydney, The Royal North Shore Hospital (Australia) | �@2010�N 2�� 6���` 2�� 21�� | 1 �� |
�T�j |
University of Hertfordshire (England) | �@2010�N 2�� 15���` 3�� 7�� | 1 �� |
�U�j |
University of California , San Francisco ( USA ) | �@2010�N 2�� 21���` 3�� 11�� | 1 �� |
�V�j |
Danish Nurses Organization, Bispebjerg Hospital (Denmark) | �@2010�N 3�� 1���` 3�� 11�� | 1 �� |
�W�j |
National Yang-Ming University (Taiwan) | �@2010�N 3�� 1���` 3�� 13�� | 1 �� |
���ʍu�`
| Public Health Nursing/Community Health Nursing in Thailand
�����F2010�N 3�� 18���i�j 14�F00 �`16�F00 �u�t�FDr. Kwanjai Amnatsatsue,PhD (Mahidol ��w���O�q���w���@�y���� , Thailand �j �ꏊ�F������Ȏ��ȑ�w�T���� 6F �@�J���t�@�����X���Q |
|
���ʍu�`
| �u�t�F
Dr. Bette Jacobs (Dean, School of Nursing & Health Studies, Georgetown University , USA ) �ꏊ�F������Ȏ��ȑ�w�T���� 15F �@��w�@�u�`���Q |
||||||||||||||
|
|
1��12��(��)�FIntroduction Student Presentation 1
|
|
1��18��(��)�FHow to add value in an interdisciplinary world
|
1��21��(��)�FHealth Law: Using the instruments of the law to improve health outcomes
|
1��22��(��)�FLeadership: The Honda Way in Health Care
|
1��22��(��)�FStudent Presentation 2 (Final Exam)
|
���ʍu�`�@ Academic Writing
�u�t�FMs. Lene Holländer �ꏊ�F������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� �g Home ��are and prevention and evaluation in Denmark �h |
| <�u�`���e> �f���}�[�N�ł͍���҂������Ԏ������Đ����ł������肪�i��ł���B�Ⴆ�f���}�[�N�ł̓��[���b�p�ŗ\�h�K���B��@�艻���Ă���A 75 �Έȏ�̑S����҂�Ώۂɍs���`��������B�^�c���@�͊e�����̂ɔC����Ă��邪�A�K����s���͍̂ݑ�Ō�t����I�ȌP�������X�^�b�t����ł���B�\�h�K��͍���҂̊�]�����f����A�p�x�̕ύX���������Ȃ����Ƃ��ł���B�]�|�̊댯����A�F�m�ǂ̑��������A����������\�ɂȂ�A�u����҂̓ƕ��ێ��A�ƕ��@�\�l���v�̖ڕW�ɂȂ���P�A���W�J����Ă���B �ݑ�×{�A�ݑ�����\�ƂȂ邽�߂ɂ͍���҂��������g�ňӎv���肵�A������x����̐��𐮂��Ă������Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��f���}�[�N�̍���҂ɑ����ÁE�����̎��ۂ��w�B |
�u�t�F Dr. Kaija Puura �ꏊ�F������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
|||||||||||||||||||
| EEPP �i European Early Promotion Project �j�w���҈琬�v���O����
�y�����\�z
|
10�� 27��
|
10�� 28��
|
10�� 29��
|
10�� 30��
|
| �u�@�t�FDr. Erlingsson, Christen�iAssociate Professor of Nursing, University of Kalmar, SWEDEN �j ��@���F������Ȏ��ȑ�w�T����15F�@��w�@�u�`���Q |
| �_�����M�ɍۂ��A�Ȋw�_���Ƃ��ĕK�v�Ƃ����G�b�Z���X��L�q�̃|�C���g�ɂ��āA�Ō�_���̋L�q��@�̃K�C�h�Ɋ�Â��A�u�`���W�J���ꂽ�B���ƌ㔼�̓f�B�X�J�b�V�����𒆐S�ɐi�߂��A�����̎���Ɠ��c���d�˂��A������[�߂邱�Ƃ��ł����B |
���ʍu�`
|
|||
�u�`�P�F���I������@�@Introduction of the contemporary major qualitative research methods |
| �u���I�����͐l���ǂ��݂�̂��v�u���I�������s���Ă������߂ɕK�v�Ȏ����v�ȂǁA���ȏ��ɂ͏����Ă��Ȃ��ADr. Fu-Jin Shih�ɂ��I���W�i���̗��_�𐔑����w�Ԃ��Ƃ��ł����B�O���E���f�b�h�E�Z�I���[����ߊw�A���ۊw��p����������@�ɂ��āA��ʓI�ȕ��@�_�ł͂Ȃ��A�S�[���͏��Publish�ɂ���Ƃ����ϓ_����ADr. Fu-Jin Shih�̍��ۊw�p���ւ̓��e�E���ǂ̉ߒ��ł̎��ۂ̌o������Ɂuaccept�Ɍ��т����I�������@�_�v�ɂ��ė�����[�߂��B���m�i�O���j�ے����甎�m�i����j�ے��܂ŁA�����̊w�����Q�������B |
�u�`�Q�F���ۊw�p�G���ւ̓��e�헪�@�|���I�����| How to conduct a research and prepare for publication in SCI/SSCI periodicals (I): Qualitative project |
| ��p��؍��ł͏C�m�ے��łP�{�A���m�ے��łQ�{�̉p��ɂ�錴���_����SCI/SSCI���x���̎G����accept����邱�Ƃ����߂��Ă���A���{��������͂����Ȃ邾�낤�Ɠ`����ꂽ�B���e�헪�̎��_����A�u�ǂ̂悤�ɍ��ǐR�����Aaccept����邩�v�ɂ��āA���ۂ̘_����reviewer�ɂ�鍸�ǂ̕������̎������g���A������[�߂��B����reviewer����̎���ɑ�����@�͔��ɎQ�l�ɂȂ����B���m�i����j�ے��̊w�������S�ɎQ�����A�w�p�I�Ȏ��₪�����Ȃ���A��Ϗ[�������u�`�ƂȂ����B |
�u�`�R�`�T�F��p�ɂ�����V�����Ō싳�� Contemporary concept of holistic care in Taiwan PBL teaching in Taiwan Taiwan 's experiences in fostering medical/nursing students' humanistic care |
| Dr. Fu-Jin Shih���Ō암���߂鍑���z����w�̉f�����ނ��������Ȃ���A��p�ɂ�����z���X�e�B�b�N�P�A�ɂ��Ċw�B��p�̑�w�ł͗l�X�ȃN���u������{�����e�B�A�����𐄐i���Ă��āA���L���N��w��E��Ƃ̌𗬂�ʂ��āA�z���X�e�B�b�N�P�A�̕��@���w��ł����B��Ð��E�҂Ƃ��ċ��߂���v�f�y�ѐl�Ԑ�����������E�҂̈琬���@�ɂ��Ď������B |
�u�`�U�F���J�u�� Open Lecture�i��@���F������Ȏ��ȑ�w�@�Տ��u���j SARS �Ƒ�n�k�ɂ�����ЊQ�Ō� Participation in international and domestic rescue plans - reflections of SARS and Taiwan 's 911 century earthquake rescuing experiences |
| Dr. Fu-Jin Shih��2003�N��SARS���s���A��p�̕a�@�ŊŌ암�������Ă����BSARS���Ҏ����̏������A���H���A�U��Ԃ���A�̂R�̒i�K�ɂ����錻��ł̑̌��A�����Ă����Ŕj���邽�߂̕���ɂ��Ċw�BSARS�������L���鋰�|�̒��A���_�I�ɂ��g�̓I�ɂ��o�ϓI�ɂ��Ɍ��̏�Ԃœ����A�����̊Ō�t�����Ƌ��ɂǂ������SARS�ɗ��������������A��̗�������ċc�_���[�߂�ꂽ�B�܂��A�p�L�X�^����n�k�Ń{�����e�B�A�X�^�b�t�Ƃ��ĕ�����Dr. Fu-Jin Shih�̑̌�����A��Ã{�����e�B�A�ɋ��߂��邱�Ƃ͎��Â����łȂ��A��Ђ����l�X�̐S�̃P�A���d�v�ł���A�ǂ̂悤�ɍs�����Ƃ��K���Ƃ����ۑ肪�Q���҂ɗ^����ꂽ�B���Ẳ��b���Ĉ�w�����W���Ă����A�W�A�̍��X�͓����A�W�A�̑����̈�Â̐i���ɍv������g���������Ă���Ƃ������b�Z�[�W����ۓI�������B |
���Đ��{�^���������Ɠ��ʍu�`�̗l�q��ł����ɂȂ�܂��B�i�vFlash player8�ȏ�j![]()
�u�`�V�F��w�E�Ō�w���̍��ۓI�{�����e�B�A���� Medical/nursing student's plans of international volunteer activities |
| ��p�ɂ�����l�X�ȃ{�����e�B�A�����ɂ��Ċw�B��p�ł͏��w������{�����e�B�A����������Ă���A���p�قł̃K�C�h��ʖ�A�C�݂̐��|�A�o�R���̒n�}�쐬�A��Y�҂̎Љ�A�ȂǗl�X�Ȋ������s���Ă���B��w���E�Ō�w���̓C���h��`�x�b�g�Ȃǂł̕ی��q��������A�����a�@�ɂ�����a�@���p�҂̈ē��Ȃǂ̃{�����e�B�A��ʂ��āA��Â̗��p�҂̃j�[�Y���w��ł����B |
�u�`�W�F����ڐA�Ō� Holistic care including physio-psycho-social-spiritual care for the OT donors, recipients and their families and how to manage ethical dilemmas. |
| ����ڐA�Ō�ɂ��ăh�i�[�E���V�s�G���g�y�т��̉Ƒ��̃P�A�ɂ��āADr. Fu-Jin Shih�̂T�̘_����ʂ��Ċw�B��p�y�ђ����ɂ����鑟��ڐA����芪�����͓��{�Ƒ傫���قȂ�A���ɒ����ł͎��Y���̑���ڐA���]���e�F����Ă��Ă���A����ڐA�Ɋւ���Ð��E�҂�Ώۂɂ�����������͑唼�̑Ώۂ��@�I�E�ϗ��I�ȋc�_�����߂Ă��邱�Ƃ��킩�����B�܂��A�����̊�@�ɂ��銳�҂ɑ���ڐA�����邩�ǂ����̈ӎv����Ɋւ��Ō�t�́A���҂̑S�l�I�w�i�𗝉����Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂ɂ͏@���I�ȗ����A�Ƒ����S���̗������܂߂��A�Z�X�����g���d�v�ł��邱�Ƃ��w�B |
�u�`�X�F���ۊw�p�G���ւ̓��e�헪 �|�~�b�N�X���\�b�h�| How to conduct a research and prepare for publication in SCI/SSCI periodicals (II) �FBetween-method triangulation project |
| �g���C�A���M�����[�V�����Ƃ͉����A�p���邱�Ƃɂǂ̂悤�ȃ����b�g������̂��A�ǂ̂悤�Ȍ����ɓK���Ă��邩�ȂǂɎn�܂�A�g���C�A���M�����[�V�����̎�@��p���č��ێ��֓��e���邽�߂̐헪���w�B���������w��ł������I�����ƗʓI������g�ݍ��킹���@�����łȂ��A���ɂ��l�X�ȃ^�C�v�̃g���C�A���M�����[�V���������邱�Ƃ��w�ׂ��B�܂��g���C�A���M�����[�V������@��p���������̌��E�ɂ��Ă��ڂ�����������B���e�G���̃��r���A�[�Ƃ̂��Ƃ�Ȃǂ̎��ۂ̃G�s�\�[�h������A���H�I�ŐV���������̑����u�`�ƂȂ����B |
�u�`10�F�a�@�ƒn������ԃ`�[����� How to integrate social support from patient's families, interdisciplinary health team in hospital & community, as well as public for dying patients |
| ��p�̍����z����w�ł́A��w�ƕa�@�����ɋ����A�g�̌��^�c����Ă����B�ی���Õ���ɂ�����ŐV�̏��⌤�������ɂ��Ēm�������L�������A�Z�~�i�[�⋳�犈�����������ĐϋɓI�ɍs���Ă���B�܂��A�n��Z���y�ѕa�@�W�ҁA����ɂ͌|�p�ƂȂǂɂ��{�����e�B�A�������n��ƕa�@�����Ԗ������ʂ����Ă���A���̑_���ƌ��ʂ͑�ώa�V�ʼn���I�ł������B |
�u�`11�F�Ō���E�҂̒���ƓW�] Challenges and future trends in Taiwan 's nursing profession |
| ����A�w���̉p��\�͂̌��オ���҂���邽�߁A���ݑ�w����Ɍg�����͍̂����p��\�͂�L���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁA���ۓI�Ȏ���������������E���犈�����s���ł��邱�ƁA�����ĕa�@�Ƒ�w�̋����A�g�͗Տ��Ō�Ɗw��I�Ō�̑o���̔��W�ɕs���ł���A�܂��d����d�v�|�X�g�𗣂�邱�ƂȂ���w�@���������V�X�e�����K�v�ł���Ƃ������Ƃ��w�B����ɁA�A�W�A�̐�i���ɂ�����O���[�o���ȖڕW�ɂ��Ă��G�ꂽ�B�A�W�A�����S�̂�����ɓ���A���W�r�㍑�ւ̉�����v���Ȃǂɂ������M�ӂ������ėՂ݁A���E�I�Ȋ������s���Ă����K�v���������������u�`�ł������B |
|
|||
�e�[�}�FApplying Attachment Theory in Early Childhood Practice�FPromoting First Relationships |
| �����Ɋւ���p��Ɠ��{��ł̊T�O�̍����A��q�̑��ݍ�p�ւ̎��ۓI�ȉ���̎d���ɂ��ĂȂǁA�킩��₷���p��œW�J����A�Q���҂̗���x�͍��������B����������݂��A�����Ȉӌ����������ꂽ�B |
�e�[�}�F���J���� Promoting First Relationships�FNurturing Caregivers to Nurture Their Young Children ��@���F������Ȏ��ȑ�w�@�J���t�@�����X�� |
| Dr. Jean Kelly�����ݕč��ŐϋɓI�Ɋ�������Ă���Promoting First Relationships�ɂ��Ċw�B�c�����̎q�ǂ��ƕ�e���邢�͕ۈ�҂Ƃ̊W�����A���̌�̎q�ǂ��̔��B�ɔ��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ͂��łɂ悭�m���Ă��邪�A���̏d�v��2�҂̊W���������ɊŌ�҂Ƃ��ĔF�m���A�W���𑣐i���邽�߂ɂǂ̂悤�ɓ��������Ă������ɂ��Ċw�т�[�߂��B�č��Ŏ��ۂɎB�e���ꂽ�e�q�W�̉f�����Q�l�ɁA���[���v���C���s������A�x���҂Ƃ��Đ�����^��⊴�z�Ȃǂɂ��ăf�B�X�J�b�V�����ł������߁A�܂��Ɂu�̊��ł���v�w�тƂȂ����B |
�p��ɂ��Ō쌤���v�揑����ј_���̍Z�{
���@�@�� |
�u�@�@�t |
|
(1) |
�@2009 �N 5 �� 7 ���A 8 ���@�@�@17:00 �` 18:00 | �@Dr. Jean Kelly |
(2) |
�@2009 �N 5 �� 14 ���A 21 ���@ 13:30 �` 16:00 | �@Dr. Fu-Jin Shih |
(3) |
�@2010 �N 1 �� 19 �� �@�@�@�@�@�@10:00 �` 12:00 �A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@14:00 �` 16:00 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@20 ���@�@�@�@�@ �@10:00 �` 12:00 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@21 ���@�@�@�@�@�@ 13:00 �` 16:00 |
�@Dr. Bette Jacobs |
�e���ł̌���ƏƂ炵���킹�A���{�Ɗe���̑̐��̔�r���m�F�������Ȃ���A�K�ȊŌ�p��̊��p���@��Ō�w�����v��̗��ĕ��@�ɂ��ċ��������B
�܂��A�w���X�ɁA���ݎ��g��ł���p��_���̍\���⌤���v�揑�̓��e�Ȃǂɂ��āA���Ԃ������ċ�̓I�Ɏw�������B |
�Ō�p��R�~���j�P�[�V�����u��
���@�@�� |
�u�@�@�t |
|
(1) |
�@2009�N 9�� 17���@ 10:00 �` 12:00 | �@Dr. Christen Erlingsson |
(2) |
�@2010�N 1�� 20���@ 14:00 �` 16:00 �@�@�@�@�@�@�@�@ 22���@ 13:00 �` 16:00 |
�@Dr. Bette Jacobs |
| (3) |
�@2010�N 3�� 19�� �@10:00 �` 12:00 | �@Dr. Kwanjai Amnatsatsue |
| (4) |
�@2010�N 3�� 25���@ 9:30 �` 10:30 | �@Ms. Helli Kitinoja,�@Mr. Aaro Harjunpää �@Dr. Asta Heikkilä,�@Dr. Harri Jokiranta |
| (5) |
�@2010�N 3�� 25���@ 14:30 �` 16:30 | �@Dr. Christen Erlingsson
�@Ms. Harriet Persson |
�Ō�p��R�~���j�P�[�V�����u���̍���̃e�[�}�́A���ۊw��ɂ�����A�J�f�~�b�N�}�i�[�����グ��ꂽ�B�Q�������w���͂���܂ł̍����O�ł̊w��\�ɂ�����o�������ӂ܂��A�������g�̍l����v�����p��ɂ���ď\���ɓ��_���邱�Ƃ��ł����B |
������20�N�x��
����20�N�x�C�O�h���w����i2009�N3��24���j
| ����20�N�x�́A�č� 6 �l�A�t�B�������h 4 �l�A�I�[�X�g�����A 1 �l�̌v 11 ���̑�w�@���̊C�O�h�����s��ꂽ�B�e�w���̊w�т̕ƁA����̌�����������H�̓W�J�ɂ��Č��������B�w���Ԃ̎��^�����������ɍs���A���N�x�̌���������Ō�̎��H�����Ă̊w�K�ӗ~�̌���ɂȂ������B |
���ʍu�`
�@ The methodology of Nursing Research By Dr. Erlingsson, Christen�i��5�`7��^�S7��j |
||
| 3 �� 6 �� | �F | �� 5 ��g Rigor in Qualitative Research �h �������ɂ�����M������x�̌���₻�̕��@�ɂ��Ă̍u�`���s�����B���Ƃ̌㔼�Ƀf�B�X�J�b�V�������s������܂ł̍u�`���e���܂߂�����ⓢ�c���s��ꂽ�B |
| 3 �� 13 �� | �F | �� 6 ��g Academic writing and publication of research �h �p��_���̍\���A��������A�w�p���ւ̓��e�ɍۂ��Ă̒��ӓ_��|�C���g�Ȃǂ̍u�`���s��ꂽ�B�u�`�㔼�ɂ�����f�B�X�J�b�V�����ł͊w�����g���p��_�������M�����Œ��ʂ��Ă���^��_�ȂǗl�X�Ȏ����A�w�����m�̈ӌ��������s��ꂽ�B |
| 3 �� 27 �� | �F | �� 7 ��g Free Discussion �h ���Ƃ�ʂ��Ď��I�����ɂ��Ẵf�B�X�J�b�V������ Dr.Erlingsson ���܂ߎQ���҂ōs�����B |
���ʍu�`
�@�@(�R�����e�[�^�[ :Dr.Erlingsson ) |
||
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
| 3 �� 5 �� | �F | �g Family nursing- a Swedish perspective of health promotion �h
�X�E�F�[�f���ł̉Ƒ��Ō�̎��ہA�w���Ō�w����ɂ�����Ƒ��Ō�̓��e�̐������s��ꂽ�B�X�E�F�[�f���̓����I�ȉƑ��Ō�̕��@���Љ��A����A���c�������������B |
| 3 �� 13 �� | �F | �g Elder Abuse and Violence in elderly care �h �X�E�F�[�f�������ł̍���ҋs�҂̌���Ɛ�s�����A Dr. Saveman �̌����̓��e���܂߂��u�`���s��ꂽ�B���Ƃ̌㔼�ɂ����ē��{�A�����S���A�X�E�F�[�f���Ԃ̍���ҕ�����s�ґΉ��̑���_�Ȃǂ̈ӌ��������s�����B |
���ʍu�`
| �u�t | �F | Dr.Tserendagva, Dalkh (Professor, Dean, School of Nursing, Health Sciences University of Mongolia)
Ms.Gaalan, Khulan (RN, MSN, Head of Nursing Department, School of Nursing, Health Sciences University of Mongolia) Ms.Sharav, Tsermaa (RN, ) |
| �e�[�} | �F | (1)�g Current Situation and future trend of Nursing education in Mongolia �h (2)�g Issues and Challengsn of Mongolian nursing �h |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
|
(1)�����S���ł̈�w�A�Ō�w����̗��j�̏Љ�A���݂̋���V�X�e���⏫���ւ̉ۑ�Ȃǂ̍u�`���s��ꂽ�B
(2)�����S���ɂ�����Љ�\���̕ω��Ƃ���ɔ����K�v�Ƃ���Ă���Ō�w����ȂǏڍׂɂ킽�錻��̐������������B�܂������S���ɂ����Ă��Ō���H�ɂ�����d�a�l�A�O���[�o�����A���E��Ƃ̘A�g���K�v�ł��邱�Ƃ��Љ�ꂽ�B �u�`�㔼�ɂ���Ƀ����S���ւ̗�����[�߂邽�߂Ƀf�B�X�J�b�V�������s���A�ӌ��������s��ꂽ�B |
���ʍu�`
�@ The methodology of Nursing Research By Dr. Erlingsson, Christen �@�i��1�` 4��^�S�V��j |
||
| 2 �� 6 �� | �F | ��1��@�g Qualitative Research �h ���I�����ɂ��Ă̑��_�̍u�`���s�����B�������Ɏg�p������Ȏ�@�A�菇�ɂ��Đ���������z�z���ꂽ��������ɎQ���҂Ńf�B�X�J�b�V�������s�����B |
| 2 �� 13 �� | �F | ��2��@�g Date collection Issues in qualitative research �h
���I�������s����ł̃f�[�^���W�ɂ�������@�_�̍u�`���s�����B�܂����Ƃ̖`���ŌʃC���^�r���[�̃f�����X�g���[�V����������A�C���^�r���[��i�߂��ł̗ϗ��I�z����C���^�r���[��@�̐��������H�I�ɍs�����B |
| 2 �� 20 �� | �F | ��3��@�g Phenomenology and Hermenuetics �h
�O��s�����C���^�r���[�̃f�����X�g���[�V�����̒���^���g�p���A���ۊw�Ɖ��ߊw�ɂ��Ă̊e�_�Ƌ��ɋ�̓I�ȗ�������Đ������B���Ƃ̍Ō�ɎQ���҂Ńf�B�X�J�b�V�������s�����B |
| 2 �� 27 �� | �F | ��4��@�g Narrative Analysis �h �i���e�B�u���T�[�`�ɂ��Ă̊e�_���s�����B�O���͍u�`���s���A�㔼�̓f�B�X�J�b�V�������s�����B���̎�@��������Č�����i�߂Ă���w�����������߁A�����Ȉӌ��������������B |
���ʍu�`
| �u�t | �F | Ms. Christen Erlingsson �i Associate Professor of Nursing, University of Kalmar, SWEDEN �j |
| �e�[�} | �F | ����ҋs�҂̗\�h�ƑΉ� |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
�X�E�F�[�f����č��ɂ����鍂��ҋs�҂Ƃ��̗\�h���@�ɂ��Ċw�B����ҋs�҂̔����Ɗւ����ɂ��āA���E��W����ی���Õ����X�^�b�t���ł��邱�Ƃɂ��ė�����[�߂��B �X�E�F�[�f����e���̕����I�w�i�A�@���x�A�Ƒ��̊W���̍\�z�ɂ������������E�Ȃǂ܂��A�ʓI�Ȋւ����̕K�v���ɂ��Ċw�B |
| �u�t | �F | �R�{���q�@�����i������Ȏ��ȑ�w��w�@�@����ҊŌ�E�P�A�V�X�e���J���w����j |
| �e�[�} | �F | ������l�����@�_ |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
�Ō쌤���������ʓI�ɏ[�����čs�����߂ɁA�ǂ̂悤�Ɍ�������l������悢�̂��A������\�[�X��l�����@�A���̊��p�@�Ȃǂɂ��āA���H�I�ȍu�`�ɂ��w�Ԃ��Ƃ��ł����B |
| ����20�N�x�u��w������v�v���O���������t�H�[�����v�Q�� | ||
| ��� | �F | �p�V�t�B�R���l |
�|�X�^�[�Z�b�V�����ɎQ�����A�{�w�ł̖{�v���O�����̎��g�݂��Љ���B�|�X�^�[�Z�b�V���������łȂ��A��u���E�p�l���f�B�X�J�b�V�����E�e�v���O�����ʂ̕��ȉ�������ɍÂ���Ă���A�����̎Q���҂ƂƂ��ɐϋɓI�Ȉӌ�������c�_�����킷���Ƃ��ł����B |
| �u�t | �F | Ms. Harriet Persson �i Health Consultant, SWEDEN �j |
| �e�[�} | �F | �X�E�F�[�f���ɂ�����n��ی��Ō슈���Ƌ��� |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�����ی��Ō�w��U ������ |
�X�E�F�[�f���ɂ�����Ō싳��V�X�e���ɂ��ċ������ꂽ�B�X�E�F�[�f���ł� District Ns( ���{�ɂ�����ی��t�����E ) ����܂̏�������L����B����炪����ꂽ�o�߂�A����ے��A���H�̎��ۂƉۑ蓙�ɂ��Ċw�B ���݂̓��{�ɂ����āA��Êi����ƒn��Â̖��A���a�\�h��ݑ��Â̑��i�A�݉@�����̒Z�k���Ȃǂ��i�ޒ��ł́A�X�E�F�[�f���� District Ns �̖����Ɋw�Ԃׂ����Ƃ͑����Ǝv��ꂽ�B |
| �u�t | �F | Ms. Helli Helena Kitinoja �i Seinajoki University of Applied Sciences, Manager of International Affairs, FINLAND �j |
| �e�[�} | �F | �t�B�������h�ɂ����鍂��҂̎������������ւ̎��� |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
�t�B�������h�ŗ͂����Ă���A����҂�����Ōp�����Ē����I�ɐ������邱�Ƃ��\�ɂ��邽�߂̍ݑ�Ō�E���E���n�r���̏[���E�����̊m�ہE�T�[�r�X�̎��̕ۏ̂�����ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł����B |
| �u�t | �F | Ms. Aila Marjatta Vallejo Medina �i Seinajoki University of Applied Sciences ����҃P�A��敔�� , FINLAND �j |
| �e�[�} | �F | �t�B�������h�ɂ����鍂��҂̃P�A�Ƌ��� |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
�t�B�������h�ōŋߊJ�n���ꂽ����҃P�A�̐��Ƃł��� Geronomist �̐��x�Ƃ��̋���Ɋւ��ċ��������B
���{�ɂ����Ă��A����҃P�A�̐��Ƃ̗{���ɂ��Ăǂ����g��ł����ׂ����A�Ō�w�̗��ꂩ��l���邱�Ƃ��ł����B
���Đ��{�^���������Ɠ��ʍu�`�̗l�q��ł����ɂȂ�܂��B�i�vFlash player8�ȏ�j![]()
| �u�t | �F | Ms. Patricia Suzan Garibaldi �i USA �j |
| �e�[�} | �F | �I���S���B�ɂ����鍂��҂̓]�|�\�h �gPrevention of falls for elderly people in Oregon�h |
| �ꏊ | �F | ������Ȏ��ȑ�w�@��w�@�u�`�� |
�I���S���B�ł̍���҂̓]�|�̌���A�����A�\�h�̉�����@�̍u�`���s�����B���ɗ\�h�@�ł́A���ۂ̍���Ҏx�����@�A�������̕��@�����������B�܂��A����҂��x���邽�߂̃`�[���A�v���[�`�̕K�v�����w�B�@
��w�E�s���ƗՏ����ꂪ�������āA����҃P�A�̎��̌����ڎw�������g�݂��s���K�v�����w�Ԃ��Ƃ��ł����B
�p��ɂ��Ō쌤���v�揑����ј_���̍Z�{
���@�@�� |
�u�@�@�t |
|
(1) |
�@2009 �N �@�E2 �� 16 ���A 23 ���A 24 �� �@�E3 �� 2 ���A 3 ���A 9 ���A 10 ���A 16 ���A 17 ���A 23 ���A 24 �� �@10:00 �` 12:00 |
�@Dr. Erlingsson, Christen |
|
(2) |
�@2009 �N 1 �� 13 �� �@10:00 �` 12:00 |
�@Dr. Erlingsson, Christen |
|
(3) |
�@2008 �N 11 �� 18 ���A 19 ���A 20 ���@ �@10:00 �` 12:00 |
�@Ms. Garibaldi, Patricia Suzan |
�e���ł̌���ƏƂ炵���킹�A���{�Ɗe���̑̐��̔�r���m�F�������Ȃ���A�K�ȊŌ�p��̊��p���@��Ō�w�����v��̗��ĕ��@�ɂ��ċ��������B
�܂��A�w���X�ɁA���ݎ��g��ł���p��_���̍\���⌤���v�揑�̓��e�Ȃǂɂ��āA���Ԃ������ċ�̓I�Ɏw�������B |
�Ō�p��R�~���j�P�[�V�����u��
���@�@�� |
�u�@�@�t |
|
(1) |
�@2009 �N �@�E2��2���A3���A16���A17���A23���A24�� �@�E3��2���A3���A9���A16���A17���A23���A 24�� �@10:00 �` 12:00 |
�@ Dr. Erlingsson, Christen |
(2) |
�@2009 �N 2 �� 4���A5���A9���A10�� �@10:00 �` 12:00�A14:00�`16:00 |
�@ Dr. Erlingsson, Christen |
(3) |
�@2009�N1��13�A15�� �@14:40 �` 16:40 |
�@ Dr. Erlingsson, Christen |
(4) |
�@2009�N1��7�A8�� �@14:40 �` 16:40 |
�@Ms. Harriet Persson �@ �@Dr. Erlingsson, Christen |
(5) |
�@2008�N12��15�A16 �A17 �A18�� �@14:40 �` 16:40 �i 12 �� 17 ���̂� 10:00 �` 12:00 �j |
�@Ms. Kitinoja, Helli �@Ms. Medina, Aila Marjatta Vallejo |
(6) |
�@2008�N11��18���A19 ���A20���@ �@14:40 �` 16:40 |
�@Ms. Garibaldi, Patricia Suzan |
�Ō�p��R�~���j�P�[�V�����u���ł̃e�[�}�́A�����Ⴄ���e�Ői�߂�ꂽ�B
�Q�������w���̉ۑ�A���݊w�����s���Ă��錤���e�[�}�A�e���̌���Ɠ��{�̌���A�e���ł̍���Ҏ{�݂�n��P�A�̌���ƊŌ슈���̉ۑ�ɂ��ĂȂǁA����̃Z�b�V�����̓��e�͑���ɂ킽�����B
���ꂼ��̊w�������g�̊Ō쌤���Ɋւ���l����v�����A�p��ɂ��\���ɓ��_�ł����B