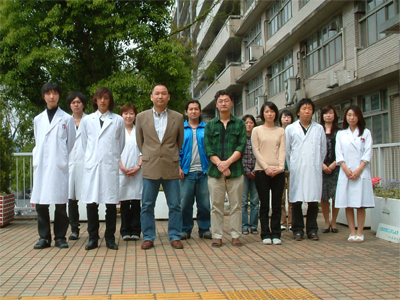現時点での主要な研究課題としては、従来から進めているチロシンキナーゼ(PTK: protein-tyrosine kinase)の下流における抑制性シグナル分子の生理機能とその破綻による造血器腫瘍や免疫疾患の解析に加え、骨格筋の運動神経支配に必須のシナプスである神経筋接合部(neuromuscular junction)におけるPTKシグナルの解析等に重点を置いている。また、当然のことながら、将来に向けた新規シグナル分子の探索や細胞内シグナル系の時空的な理解への試みは間断なく実施されている。これらの研究に用いる手法は多岐にわたり、シグナル分子複合体の精製とその同定、分子間相互作用の生化学的な解析、株化細胞、初代培養細胞や臨床検体を用いた分子生物学的解析、小型魚類や遺伝子操作マウスを用いた遺伝学的解析などが精力的に進められている。
最近の研究から、我々は独自に単離したDok-1(p62dok)とその類縁分子であるDok-2が造血及び免疫機構の恒常性の維持に必須の抑制因子として機能していることを発見した(参考文献:英文5、6/和文3、5)。また、新たなDok類縁分子としてDok-7を単離し、それが、神経筋接合部の形成に必須の機能分子であり、その異常が神経筋接合部の形成不全を伴う先天性筋無力症の原因となることを発見している(参考文献:英文1、2、3/和文1、2)。現在、これらの知見を基盤とした解析を含め、以下の各項目の研究を進めている。
- 抑制性のDokファミリー分子であるDok-1、Dok-2、Dok-3の作用機構の解析
- Dok-1/2/3ノックアウトマウスを用いた生理機能と病態生理学的機能の解析
- Dok-7を介したシグナル伝達機構の解析
- 筋無力症におけるDok-7シグナル異常の解析とその制御法の探索
- 運動神経による骨格筋の制御に重要な新規シグナル分子の探索と機能解析
- PTK型癌遺伝子産物(Bcr-Abl)によるヒト慢性骨髄性白血病の発症、及び増悪化の抑制機構に関する解析
- Dok-4、Dok-5、Dok-6の生理機能と癌やその他の疾病における病態生理学的機能の解析
当分野は大学院医歯学総合研究科並びに疾患生命科学研究部・生命情報科学教育部に属しており、意欲ある学生、ポスドク(科研費)を募集しています(詳細は e-mail にてお問い合わせ下さい)。
担当教授より:
昨年はスタッフと大学院生が一丸となって解明してくれたDok-7による神経筋シナプスの形成機構に関する論文を発表することができました(参考文献、英文3)。さらに、幸いにも、オックスフォード大学のDavid Beeson教授とAngela Vincent教授らのグループと共同で、神経筋シナプスの形成不全を伴う肢帯型の先天性筋無力症がDok-7遺伝子の両アレル性の変異によって発症することを解明しました(参考文献、英文2)。つまり、私が当分野の基軸として毎年書いている様に(次項参照)、「純粋に科学的な興味に基づいて、常に新しい知見を追求する」ことが、神経筋接合の形成に不可欠のシグナル分子であるDok-7の発見として結実し、それが、先天性筋無力症の原因遺伝子の発見と言う「新たな治療法の開発に寄与できるような知見」の獲得に発展したと言えそうです。もちろん、これらは既に過去の出来事ですから、今後も、Dok-7を介するシグナル伝達機構と、その破綻によって発症する筋無力症の分子病態の解明を急ぎ、可能な限り、その治療法の開発に貢献しなければなりません。幸いなことに、この課題に限らず、全教室員が各々の課題に真摯に取組んでいますので、今年度も、これまでの勢いを落とさぬ様、一致協力し、一歩ずつ前進してゆきます。
さて、前述の通り、研究室の発足以来毎年書いていることですが、当分野の目的は難治性疾患の克服に少しでも貢献することにあります。しかしながら、私個人の興味は広く生命現象全般に及んでいますし、我々が新たな治療法の開発に寄与できるような知見を得ることが仮に可能であるとすれば、純粋に科学的な興味に基づいて、常に新しい知見を追求する以外に道はありません。その為には、それが新しい知見をもたらすものか否かを厳しく自問しながら、自由に、研究を展開することが必要となります。その上で、研究活動にとって最も大切なことは個々の研究者が主体としてその研究を育んでいくことですから、細胞制御学分野に所属する研究者全員が、個々の課題を自分の研究として育てていけるように環境を整備し、共に悩みながら進んでゆくつもりです。
もし、我々と共に、主体として研究を進めることに少しでも興味がある場合は、いつでも御連絡いただければ有り難く思います。いっそう明るく、いっそう力強い研究室にすることが私の希望です。
(平成19年4月、山梨:Researcher database)
[参考文献]
英文
- J. Biol. Chem.: 283, 5518-5524, 2008
- Science: 313, 1975-1978, 2006
- Science: 312, 1802-1805, 2006
- Genes Cells: 11, 143-151, 2006
- J. Exp. Med.: 201, 333-339, 2005
- J. Exp. Med.: 200, 1681-1687, 2004
- Proc. Natl. Acad. Sci. USA.: 100, 7836-7840, 2003
- J. Biol. Chem.: 276, 2459-2465, 2001
- Genes & Development:14, 11-16, 2000
- Cell: 88, 205-211, 1997
和文
- 細胞工学6月号「神経筋シナプス形成と筋無力症におけるDok-7/MuSKシグナル」:p674-678, 2007
- 実験医学10月号「神経筋シナプスの形成におけるDok-7の役割:細胞内因子による受容体型キナーゼの活性化」:p2517-2520, 2006
- Molecular Medicine増刊「免疫2006」:42, 230-237, 2005
- 実験医学増刊「シグナル伝達研究2005-‘06」:23, 39-47, 2005
- 実験医学4月号「血球の恒常性とDok-1/2の新たな機能」:p1126-1132, 2005
- 実験医学増刊「キーワードでわかる シグナル伝達」:18-20, 84-94, 2004
- 実験医学増刊「シグナル伝達研究2003」:21, 35-43, 2003
- 実験医学増刊「免疫総集編2001」: 19, 116-122、2001
- 実験医学増刊「プロテオーム研究とシグナル蛋白ドメイン」: 18, 93-100、2000
連絡先 電話03(5803)5814 Fax 03(5803)0241