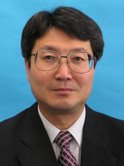先導人(せんどうびと) No.8 塙教授
私たちは、大学、研究所、研究室に所属して教育研究活動を行っており、これらの組織と個人のレベルで、成功と失敗、上昇機運、停滞、下降を、日々繰り返し、これらによる喜びと反省を感じ、ときには自暴自棄になりながら毎日を送っている。ここで、目に見えて現れる成功や失敗、成果というのは、数学的には1次微分で表される傾きであって、今後これがどのように変化していくかは、2次微分をみなければわからない。物事がうまくいっているようにみえるときでも、2次微分はマイナスに転じており、すでに衰退の徴候が現れ始めている場合がある。しかし、この徴候はすぐにはわかりくい。ましてや、成功機運にあるグループには衰退の徴候を感じ取ることは難しい。成功に味を占めた企業が同じやり方に固執したために衰退した例は枚挙に暇がない。最悪なのは、成果も出なくて2次微分もマイナスの場合で、これは自己崩壊に向かっているといえる。逆にうまくいかないようにみえても、下積みの努力が実って2次微分がプラスに転じており、この状態が続けばいずれ誰にもわかる成果となって現れてくる場合がある。この場合、1次微分がプラスに転じない期間は成果として評価されず、組織も本人も苦しむであろう。産みの苦しみである。この期間の苦しみに耐えられなければ、1次微分がプラスに転じないまま、2次微分も下降に転じてしまう。上昇傾向にあるときでも2次微分が永久にプラススということはあり得ないので、2次微分のプラスとマイナスが混在しながら、1次微分つまり目に見えて現れる成果はプラスのままであるというのが理想であろう。ところで、我が生体材料工学研究所は、現在どの状態にあるのだろうか?